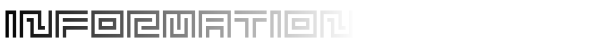10.01.00:21
[PR]
10.04.22:20
指宿高校の進学指導実績
2005年度から2007年度まで県立高校学力向上推進総合プランが実施され、2008年度からは県立高校学力向上推進プロジェクトが実施されています。
進学指導推進校13校の国公立大学の合格実績からプロジェクトを評価してみたいと思います。
県立高校学力向上推進総合プラン(2005~2007)における進学指導推進校は、以下のとおりで鹿児島市外の各学区のトップ校が指定されています。
| 学力向上推進校(8校) | 鹿児島西、枕崎、吹上、隼人工業、串良商業、鹿屋農業、垂水、奄美 |
| 進学指導推進校(13校) |
指宿、加世田、川辺、伊集院、川内、出水、大口、加治木、国分、志布志 鹿屋、種子島、大島 |
今回は、指宿高校について掲載します。
指宿高校は、県立高校学力向上推進総合プラン等の対象校13校のうちの1校です。
県立高校学力向上推進総合プラン等の効果を図るためには、プラン等が開始された平成17年度以前の平成17年3月卒業以前の高校の合格実績が必要です。
指宿高校のホームページに平成16年3月卒業生以降の合格実績が掲載されており、学力向上対策の評価を行うことができます。
平成16年3月卒業生の実績に比較して、対策前年の平成17年3月卒業生は、卒業生に対する現役合格率、全体合格率とも若干上昇していますが、対策中の平成18年3月卒業生、平成19年3月卒業生と次第に上昇し、推進プランの3ヶ年を経験した平成20年3月卒業生は、現役合格率、全体合格率とも上昇し、平成16年3月に比較して、約2倍の状況となっています。
平成21年3月卒業生は、平成19年3月並の合格率となっています。
平成22年3月卒業生は、平成21年3月卒業生より全体・現役の合格率が上昇していますが、特に国立大学の合格率が27.3%に上昇しており、平成19年の合格率24.1%を上回っています。
ただし、平成16年度以降連続して九大の合格者を出していましたが、平成22年度は合格者が出ませんでした。
平成23年度は、国立大学の現役合格率、全体の合格率とも大幅に低下しています。
このデータからすると、学力向上対策により、指宿高校においては現役合格率、全体合格率とも高まっており、一定の効果が上がっているものと推定されますが、平成23年度は若干低下傾向になっているのが気になるところです。
指宿高校の国公立大学合格実績 ( )は過年度卒業生
| 卒業年 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 |
| 卒業生数 | 229 | 198 | 196 | 187 | 152 | 152 | 139 | 129 |
| 国立大学 | ||||||||
| 鹿児島大 | 20(6) | 16(2) | 13(1) | 15 | 18(2) | 22(5) | 18(2) | 15(3) |
| 九州大 | 2(1) | 2(1) | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 神戸大 | - | - | 1 | - | - | 1(1) | - | - |
| 広島大 | 1 | 1 | - | 1(1) | - | 1 | - | - |
| 熊本大 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 宮崎大 | 2(1) | - | 4 | 3 | 2 | 1(1) | 5 | 2(1) |
| その他 | 12(1) | 18 | 8(1) | 22 | 14(2) | 11 | 16 | 6(1) |
| 小計 | 39(9) | 37(3) | 31(2) | 46(1) | 37(4) | 38(7) | 40(2) | 25(5) |
|
卒業生数に対する 国立大学合格者 (現役)の割合 |
13.1% | 17.2% | 14.8% | 24.1% | 21.7% | 20.3% | 27.3% | 15.5% |
|
卒業生数に対する 国立大学合格者 (現役・浪人含む) の割合 |
17.0% | 18.7% | 15.8% | 24.6% | 24.3% | 25.0% | 28.8% | 19.4% |
| 公立大学 | ||||||||
| 都留文科大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 下関市立大 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 北九州市立大 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 長崎県立大 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 熊本県立大 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| その他 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 8 |
| 小計 | 13 | 11 | 20 | 11 | 24 | 16 | 8 | 16 |
| 合計 | 52(9) | 48(3) | 51(2) | 57(1) | 61(4) | 54(7) | 48(2) | 41(5) |
|
卒業生数に対する 国公立大学合格者 (現役)の割合 |
18.8% | 22.7% | 25.0% | 29.9% | 37.5% | 30.9% | 33.1% | 27.9% |
|
卒業生数に対する 国公立大学合格者 (現役・浪人含む) の割合 |
22.7% | 24.2% | 26.0% | 30.5% | 40.1% | 33.6% | 34.5% | 31.8% |
| 対策実施 |
県立高校学力 向上推進総合プラン |
県立高校学力向上
推進プロジェクト
|
||||||
10.03.07:01
鹿児島県内の高校の進学指導
鹿児島県についも掲載されています。
各都道府県においても大学入試に対するいろんな取り組みを進めています。
受験生の大学進学に対するモチベーションを高めるための取り組みとして、社会や職業との関係を意識させるものが多いようです。
各高校でもいろんな取り組みが行われていますが、より効果的な取り組みとするため、公立高校、私立高校など合同で実施するなど効率的で、取り組みの機会を広げる方法が必要と考えられます。
たとえば、大学のオープンキャンパスへの参加は、東大や京大、その他の大学によっては各高校では人数が少なく、個人レベルでの対応になるところでは、旅行会社と連携し、各高校と合同で実施するなど鹿児島県全体のレベルアップを図る取り組みも必要かと考えます。
(アエラの鹿児島県に関する記事)
ラ・サール高校という全国屈指の進学校がありながら、4年制大学進学率は全国で最も低い鹿児島県。高卒後の就職率は全国平均を大きく上回る。
就職率100%を誇る鹿児島工業高校では、7割の生徒が県外に就職する。担当者は、
「大学に進学できる学力があっても、トップ層は進学しない。推薦枠を使って、大手企業に就職する。大学を出たからといって、就職が保証されるわけではありませんから」
県内屈指の進学校、鶴丸高校では、01年から県内のOBとの交流、04年からは県外のOBとの交流を図る修学旅行も兼ねた「GO鶴(かく)セミナー」に取り組んでいる。小倉寛恒校長はいう。
「今の若者たちは社会に働きかける力が弱い。何のために学び、それをどう社会に生かしていくかのか。一定のレベル以上を目指すのには、学びのインセンティブを考える必要がある」
雇用問題、進学モチベーション・・・・・・東北や九州など進学率が低い県では同じ課題を抱えている。それは本来進学熱が高いはずの高偏差値校でも、程度の差はあれ変わらない。
鹿児島市中心街から車で約1時間半走った先に、南薩摩地方の進学校、加世田高校(南さつま市)がある。
午前7時40分から8時15分までの0時間目に始まり、3年生になると、最大8時間目まで授業がある。終わりのチャイムが鳴るのは午後5時50分だ。
生徒に補習という形で学力フォローをするだけではなく、08年度からは学力推進委員となった教師を中心に教材研究や研修をする「県立高校学力向上推進プロジェクト」を県教委が始めた。生徒が目指したいと思った進路を実現できる「教師力」に力を入れる。
10.02.21:13
ラ・サール高校の進学指導
引き続き、河合塾の情報誌(2009年4月)からです。
ラ・サール高校
学年の枠を超えた交流が人間形成の上で大きな意義を持つ
1950年、カトリックの教育修道会「ラ・サール会」によって設立された。中学は4クラス、高校は6クラス。高校1年次は、内部進学者と高校からの入学者は別クラス編成で、2年次の文理分けの時点で混合クラスになる。長らく文系2クラス、理系4クラスで推移しているが、クラス数は同じでも、人数で見ると大幅な変化が生じている。
「20年前であれば文系志望者が120名ほどいましたが、今年度は約60名と半減しています。理系の中でも、医学部志望者が圧倒的に多く、それが近年の合格実績にも反映されています。また、東京大学の現役受験者数は、毎年百数十名いましたが、近年は半分近くにまで減少しています。一方で、国公立大学医学部の合格者数は、2007年度が全国でトップ、2008年度も3位になっています」(麻生善三先生)。
医学部志望者の増加に伴って、2007年度から、面接対策にも力が注がれている。3年次の10月に、医学部志望者を集めて、面接に関するレクチャーを約1時間実施。入試直前には模擬面接も行われる。
「実際に模擬面接を行ってみると、医師になるためには当然の常識と思われることが抜けている生徒も見られます。けれども、本番直前では、問題点を十分にフォローできません。今後はもっと早い時期に模擬面接を実施して、不足部分をカバーするきっかけを与える必要性を痛感しています」(麻生先生)
そのほか、同校の教育の特色になっているのが、多くの生徒が寮生活を送ることだ。「学年の枠を超えた交流が、人間形成の上で大きな意義を持っています。中学寮は8人部屋(高校寮は個室)で、各学年2~3人ずつがこの部屋で一緒に生活します。その中で、風呂の入り方などの生活のルールや、授業でのノートの取り方、予習復習の方法、寮の自習で各教科に費やす時間配分などの勉強方法についても、先輩が教える雰囲気が醸成されています。いわばラ・サールの流儀がそうやって継承されているわけです。また、中学寮には自習室があり、1日3時間、義務自習の時間が設けられています。30分の休憩をはさんで、前後90分ずつ、私語や読書は一切禁止で、集中して勉強に取り組んでいます。高校寮では生徒がそれぞれの部屋で自主的に学習します。なお、寮は高校2年生までで、3年生からは指定下宿に移ります。消灯時間が中学寮は11時、高校寮は12時と決められているので、それ以降も勉強したい生徒に配慮しています」(麻生先生)
また、近年、同校では進路意識を高めるさまざまな試みが導入されている。例えば、2年前からスタートしたのが東京大学主催「高校生のための金曜特別講座」の中継だ。東京大学の駒場キャンパスの公開講座を、インターネットでつないでリアルタイムで受講できるようにしている(同校のほか、約30高校が同時に受講)。双方向型で、質疑応答も可能で、高度な学問に触れる機会になっている。
2005年度からは「東大見学会」も実施されている。夏休みに、1・2年生の希望者を引率して、OB教員の研究室を訪問し、夜はOB学生との交歓会も行われる。寮生活を通して、親しい先輩も多いので、活発な交流が展開されている。身近な先輩の話を聞くことで、大学の様子がイメージしやすいメリットがあるという。
さらに、2008年度から、進学係主催の講演会もスタートした。「医学部入試の現状」などのテーマで、何人かの教員が講師を務め、今年度は4回実施されており、各学年から毎回100 名近い生徒が参加している。
「このように、本校では、さまざまな進路行事を増やしています。大学で何を学びたいのか、どんな職業
をめざしたいのか、明確な将来イメージを持てない生徒が近年増加しているように感じるからです。今後も、生徒一人ひとりが自分なりの方向性を見定めて、それに向かって学習のモチベーションを高められるような指導を強化していきたいと考えています」(麻生先生)
10.01.21:03
鶴丸高校の進学指導
引き続き、河合塾の情報誌(2009年4月)からです。
鶴丸高校
先輩の協力を得て実施する進路行事を豊富に設定
1894年、鹿児島県尋常中学校として創立。旧制第一中学校、第一高等女学校を前身とする伝統校で、鹿児島県で最も古い歴史を有する。1学年は普通科8クラスで、2年次から文理分けが行われる。国公立大志望者がほとんどで、例年高い合格実績を上げている。
鹿児島県の公立高校は、朝課外や放課後補習などで学習時間を確保するところが多いが、同校の場合は、朝、放課後の補習は一切行われていない。夏休み、冬休みの補習も、例えば、夏休みは1・2年次が7月末まで、3年次が8月初旬までと、他校と比較すると少なめだ。ただし、土曜日は月1~2回、「土曜悠学講座」が開講されている。1日4時限で、1・2年次は3教科、3年次は5教科の講座だ。
こうした指導体制をとっている理由を、秋元達也先生は、次のように語る。
「学力レベルの高い生徒が多いので、各自の自発的な学びを進めてほしいという期待を持っています。そのため、補習も少なくしています。2年前からは、全教科とも、それまで相応の量を課していた必修課題(いわゆる宿題)を減らす方針も打ち出しました。その結果生まれた余裕を有効に活用して、自分なりの専門的な学習を深める生徒もいます。けれども、その一方で、必修課題が与えられないと、自学自習が進められない生徒も出てきています。中学時代に塾通いをしている生徒が多く、与えられればそれなりに勉強するのですが、自主的に学ぼうとする姿勢が身についていないケースがあるのです。教員の間には、そうした生徒に対しては、ある程度強制的に勉強させることも必要だという意見もあり、今後、検討しなければならない課題だと考えています」
また、同校の進路指導で注目されるのが、卒業生を活用した進路行事が豊富に設けられていることだ。その1つが「GO鶴セミナー」だ。1年次は地元・鹿児島、2年次は修学旅行を兼ねて東京に出かけ、全生徒が先輩の職場を見学する。仕事の内容だけでなく、受験時代の体験談などを聞く機会にもなっているようで、生徒たちにも好評だ<資料8>。
1年次の10月には、鹿児島大学に在学中の先輩による「学部・学科説明会」を実施し、文理選択に役立てている。さらに、毎年、3月下旬に、その年に難関大学に現役合格した先輩を招いて、最もホットな「合格体験を聞く会」を開催。難関大学を身近な存在と感じさせ、チャレンジ意欲を高めている。
3年次の医学部志望者に対しては、鹿児島大学医学部の在学生が、面接のアドバイスも行っている。自分の体験をもとに、実際の面接で聞かれたこと、対応の方法、面接会場に持参した方がいいものなど、具体的な情報を得ることができ、大いに役立っているようだ。
「鹿児島県全体に共通する風土なのかもしれませんが、昔から、卒業生が高校に協力的で、後輩の面倒を見るのは当たり前といった雰囲気があります。例えば、本校の生徒は、国公立大学の2次試験受験のために、全国各地に出向くのですが、そこでは卒業生が待ち受けていて、大学の下見の案内なども引き受けてくださっています。とてもありがたいことであり、今後も受け継いでほしい気質だと感じています」(秋元先生)
<資料8>鶴丸高校「GO鶴セミナー」の体験談(一部抜粋)
|
●「文化庁の先輩を訪問。その多岐に渡る仕事内容、日本や世界を股にかけたやりがいのある仕事に感動を覚えました。また、進路のこと、高校時代のことについて自分の経験を交えて話していただきました。学部の選択のことや受験勉強での心構えなどを聞いて、これからの志望校・学部の決定などに際して、とても参考になりました」 ●「法律事務所の先輩を訪問。特に印象に残ったのが『社会で生きていくためには、仕事に対するやる気と、他人とコミュニケーションをとれることが必要だ』という話だ。相手を説得したり、説明したりする際のコミュニケーション能力がさまざまな場面で必要になってくるということだ。僕たちは、日頃の学校生活でもプレゼンやスピーチの機会が与えられているが、その機会をもっと大切にすべきだと感じた」 ●「NHKを訪問。TV番組の出演、生放送の見学、アフレコ挑戦などを体験しました。一番感じたことは、仕事にはいくつもの役割があり、それぞれがそれを全うすることで成り立っているということです。どれか1つが欠けてもよい仕事はできません。それは部活動にも通じるところがあるように感じました」 |
09.30.08:13
甲南高校の進学指導
引き続き、河合塾の情報誌からです。
甲南高等学校
総合的な学習の時間を活用した「KIプロジェクト」が威力を発揮
1 9 0 6 年創立の旧制第二中学校、1910年創立の第二高等女学校を前身とする伝統校。1学年は普通科8クラスで、文理分けは2年次から。文系3クラス、理系5クラスと、理系志望者が多い。例年200名以上が国公立大学に進学している。スクール・アイデンティティである「地球規模でものを考えるリーダーの育成」を実践するために、2001年度、総合的な学習の時間を活用した「KI(甲南イノベーション)プロジェクト」を立ち上げている<資料6>。
「地球規模でものを考えるリーダーに求められる資質とは何か。本校では、創造性(課題意識のある生徒)、人間性(人間理解の深い生徒)、表現力(自己表現のできる生徒)が重要だと考えました。KIプロジェクトはこの3つの資質を養成するために必要な教育を逆算して、多様な活動を推進しています」(藤崎恭一先生)
まず1年次の1学期には、現代社会の諸問題を学ぶ「テーマ学習」が行われる。1学期末には、学んだことに関する「小論文コンクール」を実施。2学期には、4回のディベートが設けられている。「1学期末の小論文は、まだ論理的でない面が多々見られますが、ディベートを経験することで大きく変化します。根拠が不確かなものは説得力が弱いため使えませんし、論理性が高くないと勝てません。曖昧な表現も不利になりますから、表現力も向上します。インターネットや書籍などで情報を収集する作業を通して、捨てる情報と生かす情報の取捨選択能力も自然と身につきます。その上で、3学期に再度、テーマ学習を行い、小論文コンクールを実施すると、見違えるほど論理的な文章に仕上げてきます」(藤崎先生)
2年次は、テーマ学習を行った後、学部・学科研究に入る。週1回のKIの時間は、それまではクラス単位の活動だが、この時点でクラスを解体し、20 ~ 50 名の進路志望系統別のグループ編成(KIグループ)になる。志望学部が近い生徒同士が集まり活動する中で、お互いに刺激を受け合う効果が期待できる。2学期半ばには、大学教員による出張講義「KIブラッシュアップセミナー」がスタート。この講義や、テーマ学習などで学んだことを参考にして、自分が研究したいテーマを設定して、2年次3学期から3年次1学期にかけて「課題研究」を進める。
課題研究の発表原稿は5月末までに作成し、まず6~7名の班内で発表会を開催。構成力、話し方など、いくつかの項目が設けられた審査用紙をもとに、生徒同士で相互評価が行われる。次いで、各班から選ばれた代表者が、KI系統グループ内で発表し、最優秀者を決定。さらに、各グループの代表者が1学期の終業式で3年生全員の前で発表し、大賞を選定する。大賞受賞者は、9月の文化祭で後輩や保護者の前で発表することになっている。
「リーダーとしての資質養成が目的であり、必ずしも入試に直結しているわけではないのですが、志望進路に変化が見られることも事実です。プロジェクト活動を通して、将来学びたいことが明確になり、意欲が高まった結果、難関大学を目指す生徒が着実に増えているのです。生徒にどんどん教え込んで鍛えることが、学力を伸ばす最適な方法だと考える指導体制の時期もありましたが、より効果的なのは、自分で学ぼうという気持ちを強めることではないかと思います」(藤崎先生)
もう1つ、特筆しておきたいのは、このプロジェクトがうまく機能するために、教員の負担軽減に配慮されているということだ。テーマ学習、ディベート、課題研究それぞれに、詳細な冊子を作成。例えばディベートなら、進行に関するセリフは全て記載されており、内容に関わる部分だけをリサーチして発言すればいいようになっている<資料7>。これならディベート指導に慣れていない教員でも十分に指導できるし、生徒にとっても、ルールについての理解に時間をとられることなく、学びの中身を深めることに重点が置けるわけだ。
なお、同校では、このKIプロジェクトと、大学進学に向けた学力強化を、進路指導の2本柱としているが、「KIプロジェクトが、いわば『ビタミン剤』の役割を果たし、大学進学に向けた学力強化にも少なからず好影響を与えているのではないかと思います」と藤崎先生は語る。例えば補習は、始業前に1年次は週5日、3教科で実施。2年次以降は必要に応じて、柔軟に他教科の補習も取り入れている。さらに3年次からは放課後講座、土曜講座も加わる。これらの講座は、自分の志望大学・学部にターゲットを絞った講座が選択できるようになっている。そのため、3年次には強制されて仕方なく補習を受けているという感覚は薄く、積極的に学ぼうという雰囲気が生まれているという。そのほか、日常生活における読書の習慣化を図る「朝の読書」や、各界の第一線で活躍中の卒業生を招いて、ものの見方や考え方、仕事への思いなどを語ってもらう「甲南塾」なども実施されている。
09.29.08:03
鹿児島玉龍高校の進学指導
引き続き、河合塾の情報誌からです。
鹿児島玉龍高校
中高連携、高大連携を図り活発なキャリア教育を推進
1940年創立の鹿児島市立の普通科高校。2006年度に中学校が設置され、併設型公立中高一貫教育校になった。中学は1学年3クラス、高校は6クラスである。「中学段階では、私立の一貫校のような極端なカリキュラムの前倒しは行っていません。基礎基本重視を心がけています。なお、教員は、基本的には中学と高校で別なのですが、中学3年生だけは、中学と高校の教員が相互乗り入れして、授業の一部を担当しています。中学生の学力状況などを事前に把握した上で、スムーズに高校の学習に入れるようにするためです。私も中学の授業を担当しているのですが、かなり進学意識が高く、高い志望を持つ生徒も多いようです。予習・復習の取り組みもしっかりしていますし、図書館の貸し出し数が急増するなど、読書意欲も旺盛です。今年から中高一貫の第一期生が入学してきますが、相応の学力を備えていることが期待できそうです。高校からの入学者とは学力が異なるケースもありうるので、まず、高校1年次では別クラス編成にして、2年次の文理分けの際に混在させる予定です」(坂本昌弥先生)
同校の大きな特色といえるのが、中高一貫校になったことを契機として、2006年度からスタートした多様なキャリア学習「鹿児島玉龍キャリア教育プロジェクト」だ。「鹿児島大学や九州大学など、学部・学科の多い総合大学と連携し、さまざまな学問分野を本校の日常の教育内容に取り込むことによって、大学・大学院の仕組みを理解することを目的としています。現在の学問体系は、高度化、複雑化、学際化しており、特に最先端科学は、予備知識のない中学生・高校生には理解しにくい面があります。早めに多様な学問分野に触れるチャンスを与えることで、将来の選択肢の幅が広がるはずです」(坂本先生)。例えば、2006年度は、夏休みに高校1・2年生589名、中学生120名が鹿児島大学に集合。延べ28におよぶ連携講座を受講した<資料4 >。90分講義を1講座として、2講座受講できる形だ。生徒へのアンケート調査の結果を見ると、受講前後で意識が大きく変化しており<資料5 >、学問への興味・関心の喚起につながっていることが分かる。
また、東京大学、九州大学、九州工業大学、熊本大学などの出前講座も実施している。ユニークなのは、各講師に3タイプの講座を連続で担当してもらうように依頼していることだ。中学生用、高校生用、および中学・高校の保護者用の3タイプだ。生徒用は学問の中身や、学部・学科紹介、保護者用の講座は大学の特色や、入試制度の説明などが主体になっている。さらに、中学2年生の3学期には、九州大学に出向いて連携講座を受講。中学3年生の3学期には、東京大学など、首都圏の難関大学の見学と連携講座の受講も行われている。補習の体制も注目される。全学年ともに、7時45分から8時15分まで、問題演習を中心とした朝課外を実施。放課後は、3年次の高校総体以降、3回の「放課後特訓」が行われる。「各回1カ月間、1教科だけに集中して鍛える講座です。苦手教科、あるいは逆にさらに伸ばしたい教科を生徒が選択して、徹底的に学習させています。1カ月あれば、基礎基本から問題演習まで、体系的な指導を行うことができ、着実に成果があがっています」(坂本先生)
<資料4>玉龍高校2006年鹿児島大学連携講座一覧
高校学校対象
| 文理 | 対象学部 | 担当教員 | 内 容 | 希望者数 |
| 文 | 法文学部 | 皆村 武一 | グローバル時代の鹿児島の経済と社会 | 52 |
| 文 | 法文学部 | 竹岡 健一 | 英語からドイツ語へ | 108 |
| 文 | 教育学部 | 内田 芳夫 | 障害児の発達と教育 | 24 |
| 文 | 教育学部 | 伊藤 正 | 西洋古代史 | 44 |
| 文 | 教育学部 | 岡田 猛 | 人は、なぜ体育・スポーツを行い、そこから何を得ているか | 73 |
| 文理 | 医学部 | 清水 佐智子 | 成人看護学 ハンドマッサージでリラックス | 145 |
| 理 | 理学部 | 新森 修一 | 情報ネットワーク | 22 |
| 理 | 理学部 | 根建 心具 | 宇宙人はいるか? | 161 |
| 理 | 理学部 | 今井 裕 | 天文学の世界 | 12 |
| 理 | 理学部 | 橋爪 健郎 | 自然エネルギーと平和な世界 | 7 |
| 理 | 理学部 | 清原 貞夫 | 動物の超能力 | 83 |
| 文理 | 理学部 | 河野 元治 | 地球環境に対する新たな視点 | 5 |
| 理 | 理学部 | 今井 裕 | 天文学の世界 | 33 |
| 理 | 理学部 | 橋爪 健郎 | 自然エネルギーと平和な世界 | 31 |
| 文理 | 理学部 | 河野 元治 | 地球環境に対する新たな視点 | 27 |
| 理 | 農学部 | 富永 茂人 | おいしい果実ができる謎 | 149 |
| 理 | 農学部 | 鈴木 秀作 | 動物実験と動物モデル | 63 |
<資料5>玉龍高校
連携講座受講前後の生徒の意識の変化
講座内容が将来の進路選択に役立ちそうか
| 区分 | はい | いいえ |
| 講座前 | 61 | 39 |
| 講座後 | 97 | 3 |
09.28.18:01
鹿児島県立高校の学力向上対策
鹿児島県内の卒業生数は、昭和50年度に対して60%程度となっていることから、卒業生数の比率からみると1.9%~8.8%難関大学合格者数の割合が低下しています。
一方、私立高校の台頭によって、鹿児島県全体の難関大学の合格者数の割合は、昭和50年度に対して71.9%~79.3%まで上昇しており、卒業生数の割合60%より11.9%~19.3%高くなっています。
なお、公立高校の国立大学の合格者数は、昭和50年度の合格者数に対して80%程度となっており、卒業生数の割合からすると20%程度上昇しています。
このため、公立高校の学力向上対策が課題となっています。
鹿児島県の高校教育に関する情報は、各種情報誌に掲載されています。
今回は、過去に掲載した記事を再掲します。
(2009年9月 河合塾情報誌)
先輩から後輩へ継承される学びの姿勢
「郷中教育」の精神
中高連携を活発化させる県の取り組み
鹿児島県では現在、県全体としての取り組みが活発化している。学力向上面に関連しては、2005年度から2007年度にかけて、「県立高校学力向上推進総合プラン」が推進された。
主な取り組みとしては、まず、学力向上推進校8校、進学指導推進校13校が指定された<資料1>。学力向上推進校には専門高校、進学指導推進校には普通科系の高校が指定されており、県全体としての学力の向上を目的としている。指定された高校では、延べ37回の公開授業や、教科研究会などを実施。公開授業は中学教員も参観できるようにするとともに、教科研究会も中学・高校合同で進めるなど、中高連携が進められている。
「鹿児島県進学指導ステップアップ研究会」の設立
県内の難関大学志望者が一堂に会する「郷中 ゼミ」
先輩が後輩を教育する独自の風土が根づく
そうした先輩、後輩の人間関係が情勢されていることが、鹿児島県の大きな強みといえるだろう。
以上、見えてきた受験風土を踏まえて、鹿児島県の各高校では、どのような進路指導が実施されているのか、具体的に見てみることにしよう。
<資料1> 県立高校学力向上推進総合プラン(2005~2007)における推進指定校
| 学力向上推進校(8校) | 鹿児島西、枕崎、吹上、隼人工業、串良商業、鹿屋農業、垂水、奄美 |
| 進学指導推進校(13校) |
指宿、加世田、川辺、伊集院、川内、出水、大口、加治木、国分、志布志 鹿屋、種子島、大島 |
09.27.18:37
2012年度 第1回 東大即応オープン(2011年8月実施)
鹿児島県内高校出身のA判定者は、平成23年度は22人で、平成22年度の16人対して6人増加しています。
鹿児島県内高校出身者(A判定)
| 類 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||
| 順位 | 得点 | 氏 名 | 性別 | 順位 | 得点 | 氏名 | 性別 | |
| 文科一類 | 12 | 301 | KY | 男 | 74 | 255 | HN | 男 |
| 66 | 275 | TY | 女 | 101 | 249 | UA | 男 | |
| 151 | 259 | MS | 男 | 133 | 244 | SA | 男 | |
| 164 | 256 | MY | 男 | 147 | 242 | NY | 女 | |
| 178 | 253 | SA | 男 | 180 | 236 | TY | 男 | |
| 206 | 233 | NS | 男 | |||||
| 文科二類 | 95 | 243 | KT | 男 | 65 | 237 | EY | 男 |
| 99 | 242 | HN | 男 | |||||
| 文科三類 | 4 | 291 | ES | 男 | 40 | 241 | KS | 男 |
| 理科一類 | 197 | 238 | TM | 男 | 79 | 248 | NT | 男 |
| 479 | 211 | HK | 男 | 104 | 242 | AK | 男 | |
| 506 | 210 | NM | 女 | 226 | 227 | HK | 男 | |
| 294 | 221 | YK | 男 | |||||
| 314 | 219 | NY | 男 | |||||
| 404 | 212 | NS | 男 | |||||
| 478 | 208 | ST | 男 | |||||
| 592 | 201 | TS | 男 | |||||
| 592 | 201 | KR | 男 | |||||
| 615 | 200 | IM | 男 | |||||
| 理科二類 | 51 | 245 | IA | 男 | 17 | 252 | YY | 男 |
| 149 | 221 | OK | 女 | 62 | 226 | KS | 男 | |
| 158 | 220 | TY | 男 | 131 | 205 | KS | 男 | |
| 167 | 219 | NN | 男 | |||||
| 199 | 214 | DT | 男 | |||||
| 理科三類 | 5 | 337 | HN | 男 | ||||
09.26.20:51
2012年度 第1回 東大即応オープン(2011年8月実施)
これは、あくまで8月時点の学力での評価であって、今後の学力の伸びを想定して基準を定めたものではありません。
8月時点では、高卒者の学力が高い状況ですが、11月の東大模試、入試本番時点では、現役と高卒者の学力レベルはかなり縮まり、逆転するケースが出てきます。
2001年の東京大学新聞が入学者を対象にした「最後に受けた東大模試の判定」を集計した結果を見ると以下のようになっています。
A 41% B 21% C 21% D 12% E 5%
つまり、11月の東大模試がC判定以下の者が入学者に占める割合が38%(現役の場合40%)を占めていることとなり、8月時点のC判定以下の評価は気にすることなく、11月の東大模試の各科目ごとの目標点数の設定と目標点数に達するような勉強方法の検討が重要になってきます。
合格可能性評価
A判定・・・合格可能性80%以上。合格圏到達。
B判定・・・合格可能性60%。合格圏到達直前。
C判定・・・合格可能性40%。要努力圏。
D判定・・・合格可能性20%
2011・2012年度 第1回 東大即応オープン(2010年8月実施)
| 類 | 年度 | 定員 | 配点 | A | B | C | D | |||
| 基準点 | 偏差値 | 基準点 | 偏差値 | 基準点 | 偏差値 | 基準点 | ||||
| 文科一類 | 2012 | 401 | 440 | 232点以上 | 63.4 | 219点以上 | 60.4 | 206点以上 | 57.5 | 205点以下 |
| 2011 | 401 | 440 | 246点以上 | 64.0 | 228点以上 | 60.3 | 219点以上 | 58.5 | 218点以下 | |
| 文科二類 | 2012 | 353 | 440 | 230点以上 | 62.9 | 216点以上 | 59.7 | 201点以上 | 56.3 | 200点以下 |
| 2011 | 353 | 440 | 241点以上 | 63.0 | 224点以上 | 59.5 | 206点以上 | 55.8 | 205点以下 | |
| 文科三類 | 2012 | 469 | 440 | 229点以上 | 62.7 | 210点以上 | 58.4 | 188点以上 | 53.4 | 187点以上 |
| 2011 | 469 | 440 | 237点以上 | 62.1 | 217点以上 | 58.1 | 192点以上 | 53.0 | 191点以下 | |
| 理科一類 | 2012 | 1108 | 440 | 200点以上 | 59.9 | 190点以上 | 58.0 | 168点以上 | 53.8 | 167点以上 |
| 2011 | 1108 | 440 | 207点以上 | 59.0 | 198点以上 | 57.3 | 176点以上 | 53.1 | 175点以下 | |
| 理科二類 | 2012 | 532 | 440 | 195点以上 | 59.0 | 185点以上 | 57.0 | 162点以上 | 52.6 | 161点以上 |
| 2011 | 532 | 440 | 206点以上 | 58.8 | 198点以上 | 57.3 | 175点以上 | 52.9 | 174点以下 | |
| 2012 | 100 | 440 | 286点以上 | 76.4 | 253点以上 | 70.1 | 230点以上 | 65.7 | 229点以上 | |
| 理科三類 | 2011 | 98 | 440 | 289点以上 | 74.5 | 266点以上 | 70.2 | 246点以上 | 66.4 | 245点以下 |
09.25.18:46
2012年度 第1回 東大即応オープン(2011年8月実施)
模試の平均点は、4教科440点満点で文科173.2点(2011年度 177.4点)、理科148.3点(2011年度 159.7点)となっています。
8月時点では、三教科(英語、数学、国語)320点満点で、文系で140点程度(文Ⅰ150点程度)、理系で130点程度(理Ⅲ175点程度)あれば、今後の3教科と社会・理科の伸びで現役での合格の可能性もあります。
また、3教科の得点が文系の120点~140点、理系の110点~130点のグレイゾーンであっても、対策を講じていなかったため点数が低くなったことが要因で、今後伸びが期待できる科目、分野があれば、合格の可能性はあります。
【文 科】
| 年度 | 配点 | 平均点 |
標準 偏差 |
平均偏差値 |
最高 点 |
最低 点 |
人数 | |||||||
| 全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | ||||||
| 二次総合 | 2012 | 440 | 173.2 | 166.5 | 187.4 | 44.0 | 50.0 | 48.5 | 53.2 | 348 | 22 | 4353 | 2948 | 1405 |
| 2011 | 440 | 177.4 | 171.2 | 189.4 | 49.1 | 50.0 | 48.7 | 52.4 | 348 | 11 | 4545 | 2994 | 1551 | |
| 三教科 | 2012 | 320 | 127.6 | 124.5 | 134.1 | 31.3 | 50.0 | 49.0 | 52.1 | 238 | 7 | 4353 | 2948 | 1405 |
| 2011 | 320 | 137.3 | 135.0 | 141.9 | 37.4 | 50.0 | 49.4 | 51.2 | 267 | 11 | 4542 | 2992 | 1550 | |
| 英語文系 | 2012 | 120 | 49.7 | 48.2 | 52.9 | 16.3 | 50.0 | 49.1 | 51.9 | 107 | 4 | 4310 | 2930 | 1380 |
| 2011 | 120 | 55.4 | 53.8 | 58.3 | 18.9 | 50.0 | 49.2 | 51.5 | 112 | 5 | 4503 | 2967 | 1536 | |
| 数学文系 | 2012 | 80 | 33.6 | 32.7 | 35.4 | 12.6 | 50.0 | 49.3 | 51.4 | 80 | 0 | 4338 | 2938 | 1400 |
| 2011 | 80 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 15.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 80 | 0 | 4516 | 2972 | 1544 | |
| 国語文系 | 2012 | 120 | 45.1 | 44.1 | 47.1 | 10.5 | 50.0 | 49.0 | 51.9 | 80 | 2 | 4340 | 2941 | 1399 |
| 2011 | 120 | 56.2 | 55.4 | 57.7 | 11.2 | 50.0 | 49.3 | 51.3 | 94 | 4 | 4524 | 2978 | 1546 | |
| 日本史 | 2012 | 60 | 26.8 | 25.2 | 30.3 | 9.4 | 50.0 | 48.3 | 53.8 | 52 | 0 | 2467 | 1692 | 775 |
| 2011 | 60 | 19.8 | 17.9 | 23.2 | 8.6 | 50.0 | 47.8 | 54.0 | 45 | 0 | 2533 | 1654 | 879 | |
| 世界史 | 2012 | 60 | 20.4 | 18.1 | 25.5 | 10.3 | 50.0 | 47.7 | 54.9 | 51 | 0 | 3741 | 2550 | 1191 |
| 2011 | 60 | 18.0 | 15.6 | 22.9 | 10.3 | 50.0 | 47.7 | 54.7 | 52 | 0 | 3859 | 2584 | 1275 | |
| 地理 | 2012 | 60 | 23.4 | 22.0 | 26.3 | 7.7 | 50.0 | 48.2 | 53.8 | 59 | 0 | 2393 | 2550 | 1191 |
| 2011 | 60 | 24.4 | 23.2 | 26.6 | 8.3 | 50.0 | 48.5 | 52.6 | 48 | 0 | 2582 | 1670 | 912 | |
【理 科】
| 年度 | 配点 | 平均点 | 標準偏差 | 平均偏差値 | 最高点 | 最低点 | 人数 | |||||||
| 全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | ||||||
| 二次総合 | 2012 | 440 | 148.3 | 143.2 | 159.9 | 52.1 | 50.0 | 49.0 | 52.2 | 423 | 2 | 6437 | 4455 | 1982 |
| 2011 | 440 | 159.7 | 155.1 | 170.2 | 52.7 | 50.0 | 49.1 | 52.0 | 412 | 2 | 6146 | 4296 | 1850 | |
| 三教科 | 2012 | 320 | 112.9 | 110.8 | 117.7 | 36.8 | 50.0 | 49.4 | 51.3 | 305 | 2 | 6434 | 4454 | 1980 |
| 2011 | 320 | 129.4 | 127.3 | 134.3 | 41.2 | 50.0 | 49.5 | 51.1 | 294 | 2 | 6145 | 4295 | 1850 | |
| 英語理系 | 2012 | 120 | 45.1 | 44.4 | 46.7 | 16.5 | 50.0 | 49.6 | 51.0 | 119 | 0 | 6362 | 4426 | 1936 |
| 2011 | 120 | 51.3 | 50.3 | 53.7 | 18.8 | 50.0 | 49.5 | 51.3 | 112 | 0 | 6080 | 4265 | 1815 | |
| 数学理系 | 2012 | 120 | 39.4 | 37.8 | 42.9 | 19.7 | 50.0 | 49.2 | 51.8 | 116 | 0 | 6401 | 4434 | 1967 |
| 2011 | 120 | 44.0 | 42.8 | 46.8 | 21.4 | 50.0 | 49.5 | 51.3 | 120 | 0 | 6115 | 4278 | 1837 | |
| 国語理系 | 2012 | 80 | 29.3 | 29.1 | 29.7 | 8.8 | 50.0 | 49.8 | 50.5 | 80 | 0 | 6394 | 4434 | 1960 |
| 2011 | 80 | 35.0 | 34.8 | 35.4 | 9.2 | 50.0 | 49.7 | 50.5 | 76 | 2 | 6111 | 4276 | 1835 | |
| 物理 | 2012 | 60 | 20.1 | 18.1 | 24.9 | 11.7 | 50.0 | 48.3 | 54.1 | 60 | 0 | 5713 | 3990 | 1723 |
| 2011 | 60 | 14.6 | 13.3 | 17.8 | 8.5 | 50.0 | 48.5 | 53.8 | 60 | 0 | 5455 | 3867 | 1588 | |
| 化学 | 2012 | 60 | 15.4 | 14.1 | 18.5 | 9.2 | 50.0 | 48.7 | 52.7 | 59 | 0 | 6278 | 4390 | 1888 |
| 2011 | 60 | 15.2 | 14.1 | 17.7 | 8.4 | 50.0 | 48.7 | 53.0 | 60 | 0 | 5998 | 4236 | 1762 | |
| 生物 | 2012 | 60 | 23.6 | 22.4 | 25.9 | 8.7 | 50.0 | 48.7 | 52.7 | 52 | 2 | 664 | 442 | 222 |
| 2011 | 60 | 22.9 | 21.2 | 25.6 | 10.8 | 50.0 | 48.4 | 52.5 | 56 | 0 | 646 | 402 | 244 | |
| 地学 | 2012 | 60 | 15.6 | 16.1 | 15.3 | 10.7 | 50.0 | 50.5 | 49.8 | 44 | 0 | 41 | 14 | 27 |
| 2011 | 60 | 22.2 | 15.0 | 24.9 | 13.9 | 50.0 | 44.8 | 51.9 | 47 | 0 | 30 | 8 | 22 | |
09.24.21:21
2011年度 第1回 東大即応オープン(2011年8月)
今回の受験者数は、10,790人で昨年の10,691人より99人多くなっています。
この受験者数は、2011年の東大前期日程志願者数9,779人(2010年 9,439人),二次試験受験者8,679人(2010年度 8,669人)を上回る人数であり、現役と高卒者の割合2:1も本試験と同じ割合となっています。
また、昨年は鹿児島県では、ラ・サール高校106人(一昨年150人)、鶴丸高校122人(一昨年同数)が受験しています。
受験者数の出身地区分比率は、2011年度の前期東大合格者の割合に近く、質の面からも東大入試を再現できたと河合塾は評価しています。
2009・2010年度実施 第1回東大即応オープン模試 受験者トップ20校
| 高校名 | 2009 | 2010 | 高校名 | 2009 | 2010 |
| 開成 | 274 | 265 | 渋谷教育学園幕張 | 124 | 114 |
| 西大和学園 | 184 | 116 | 鶴丸 | 122 | 122 |
| 灘 | 174 | 159 | 愛光 | 119 | - |
| 麻布 | 166 | 150 | 栄光学園 | 118 | 129 |
| 聖光学院 | 158 | 152 | 筑波大附属駒場 | 115 | 131 |
| ラ・サール | 150 | 106 | 浅野 | 105 | - |
| 海城 | 133 | 111 | 桜陰 | 102 | 110 |
| 駒場東邦 | 132 | 164 | 久留米付設大 | 101 | 144 |
| 桐蔭学園 | 132 | 109 | 岡崎 | 100 | 105 |
| 東京学院大学付属 | 128 | 126 | 栄東 | 99 | - |
| 巣鴨 | - | 115 | |||
| 土浦第一 | - | 102 | |||
| 日比谷 | - | 96 |
出身地区別比率 %
| 区 分 | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中部・北陸 | 近 畿 | 中四国 | 九 州 | その他 |
|
2012度第1回 東大即応オープン模試受験者 |
1.8 | 4.0 | 53.4 | 13.0 | 8.6 | 8.0 | 9.7 | 1.5 |
| 2011度東大合格者(前期) | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 13.1 | 14.3 | 7.8 | 8.3 | 0.2 |
|
2011年度第1回 東大即応オープン模試受験者 |
1.9 | 4.1 | 51.5 | 12.5 | 10.0 | 8.2 | 10.3 | 1.5 |
| 2010年度東大合格者(前期) | 1.7 | 3.1 | 50.9 | 14.8 | 13.3 | 8.0 | 7.9 | 0.3 |
09.23.15:33
進研模試(平成23年7月 高1 記述)
高校入学後最初に実施されるのが、7月に実施される進研模試です。
鶴丸高校の平成20年度以降4カ年間の平均点と偏差値を掲載してみます。
平成22年度は不明ですが、過去3年間では3教科の平均偏差値が1.2.から1.3程度、平成23年度が低下しています。また、3教科とも偏差値が低下しています。
鶴丸高校 進研模試(高1 記述式)の平均点・偏差値
| 高校 | 年度 | 対象 | 時期 | 平均点 | 偏差値 | ||||||
| 3教科合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 3教科 | 国語 | 数学 | 英語 | ||||
| 鶴丸 | 23年度 | 高1 | 7月 | 175.2 | 53.3 | 58.6 | 63.3 | 65.8 | 63.9 | 62.4 | 65.0 |
| 鶴丸 | 22年度 | 高1 | 7月 | ||||||||
| 鶴丸 | 21年度 | 高1 | 7月 | 196.3 | 70.5 | 59.7 | 66.1 | 67.0 | 64.4 | 63.6 | 66.8 |
| 鶴丸 | 20年度 | 高1 | 7月 | 193.3 | 59.8 | 57.3 | 76.2 | 67.1 | 65.3 | 63.4 | 65.9 |
| 全国 | 23年度 | 高1 | 7月 | 105.2 | 33.8 | 35.2 | 36.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 全国 | 22年度 | 高1 | 7月 | ||||||||
| 全国 | 21年度 | 高1 | 7月 | 117.3 | 47.5 | 33.1 | 36.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 全国 | 20年度 | 高1 | 7月 | 115.8 | 38.6 | 31.9 | 45.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
09.22.07:03
2011/2012 東大入試実戦模試 第1回(8月)
鹿児島県内高校出身の成績優秀者について掲載します。成績優秀者は、A判定の中で上位者で、今回は12人で、昨年8月の8人に比較して4人増加しています。
2011/2012東大入試実戦模試(第1回 8月)
鹿児島県内高校出身者(A判定の上位者)
| 類 | 順位 | 得点 | 氏 名 | 現卒 | 性別 |
| 文科一類 | 14 | 275 | HN | 卒 | 男 |
| 20 | 270 | TY | 現 | 男 | |
| 26 | 262 | NY | 卒 | 女 | |
| 62 | 245 | UA | 現 | 男 | |
| 65 | 244 | TS | 現 | 男 | |
| 107 | 234 | MK | 卒 | 男 | |
| 文科二類 | 45 | 229 | YJ | 現 | 男 |
| 理科一類 | 66 | 255 | OS | 現 | 男 |
| 159 | 237 | YT | 現 | 男 | |
| 理科二類 | 69 | 227 | KS | 現 | 男 |
| 91 | 222 | SS | 卒 | 男 | |
| 理科三類 | 5 | 337 | HN | 現 | 男 |
09.21.22:30
2011/2012 東大入試実戦模試 第1回(8月)
2011/2012 東大入試実戦模試(第1回)8月の合格判定基準について掲載します。
合格判定基準
A 合格確実ライン 80%以上
B 合格可能ライン 60%以上
C チャレンジライン 40%以上
D 一層の努力ライン 20%以上
【前期】
2011/2012 東大入試実戦模試(第1回)8月の合格判定基準
| 科類 | 年度 | 配点 |
合格確実ライン (80%以上) |
合格可能ライン (60%以上) |
チャレンジライン (40%以上) |
一層の努力ライン (20%以上) |
||||
| 偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | |||
| 文科一類 | 2011 | 440 | 63.5 | 449 | 60.1 | 785 | 55.4 | 1424 | 50.2 | 2345 |
| 2010 | 440 | 64.1 | 428 | 60.2 | 750 | 55.6 | 1375 | 50.6 | 2265 | |
| 文科二類 | 2011 | 440 | 61.6 | 639 | 58.2 | 1025 | 53.0 | 1821 | 48.9 | 2555 |
| 2010 | 440 | 62.5 | 565 | 58.4 | 978 | 53.1 | 1797 | 49.0 | 2581 | |
| 文科三類 | 2011 | 440 | 61.0 | 709 | 56.4 | 1281 | 52.0 | 1993 | 48.0 | 2740 |
| 2010 | 440 | 60.2 | 750 | 55.8 | 1335 | 51.7 | 2057 | 48.3 | 2719 | |
| 理科一類 | 2011 | 440 | 61.1 | 1215 | 57.6 | 1920 | 53.9 | 2868 | 50.1 | 4036 |
| 2010 | 440 | 60.7 | 1212 | 56.8 | 1980 | 52.5 | 3011 | 48.9 | 4201 | |
| 理科二類 | 2011 | 440 | 58.7 | 1634 | 54.9 | 2564 | 51.2 | 3678 | 47.1 | 5147 |
| 2010 | 440 | 59.3 | 1461 | 54.8 | 2454 | 51.2 | 3439 | 47.3 | 4756 | |
| 理科三類 | 2011 | 440 | 74.6 | 102 | 70.6 | 236 | 67.1 | 440 | 62.5 | 842 |
| 2010 | 440 | 75.2 | 104 | 70.9 | 227 | 66.1 | 522 | 62.3 | 966 | |
※偏差値・席次は、文系-4教科歴2、理系-4教科理2のものです。
東大入試実戦模試
| 年度 | 2010 | 2011 |
| 文系 | 156.5 | 156.8 |
| 理系 | 132.9 | 150.3 |
2011/2012 東大入試実戦模試(第1回)8月の合格判定基準(得点換算)
| 科類 | 年度 | 配点 |
合格確実ライン (80%以上) |
合格可能ライン (60%以上) |
チャレンジライン (40%以上) |
一層の努力ライン (20%以上) |
| 文科一類 | 2011 | 440 | 213 | 199 | 180 | 158 |
| 2010 | 440 | 218 | 201 | 181 | 159 | |
| 文科二類 | 2011 | 440 | 205 | 191 | 169 | 152 |
| 2010 | 440 | 211 | 193 | 170 | 152 | |
| 文科三類 | 2011 | 440 | 203 | 183 | 165 | 149 |
| 2010 | 440 | 201 | 182 | 164 | 149 | |
| 理科一類 | 2011 | 440 | 204 | 187 | 169 | 151 |
| 2010 | 440 | 180 | 163 | 144 | 128 | |
| 理科二類 | 2011 | 440 | 193 | 174 | 156 | 136 |
| 2010 | 440 | 174 | 154 | 138 | 121 | |
| 2011 | 440 | 270 | 251 | 234 | 211 | |
| 理科三類 | 2010 | 440 | 244 | 225 | 204 | 187 |
09.20.22:40
2011/2012 東大入試実戦模試 第1回(8月)
過去2年間のデータも参考までに掲載します。
文系
| 教科・コース | 年度 | 配点 | 平均点 |
偏差値現卒差 (現役-既卒) |
受験者数 | 標準偏差 | ||||
| 全体 | 現役 | 既卒 | 全体 | 現役 | 既卒 | |||||
|
4教科歴2コース (英・数・国・歴2) |
11 | 440 | 156.8 |
151.5 (48.7) |
168.3 (52.8) |
-4.1 | 4,898 | 3,373 | 1,525 | 41.6 |
| 10 | 440 | 156.5 |
151.0 (48.7) |
168.3 (52.7) |
-4.0 | 4,895 | 3,362 | 1,533 | 43.8 | |
| 09 | 440 | 163.7 |
158.0 (48.8) |
175.3 (52.4) |
-3.6 | 5,259 | 3,548 | 1,711 | 48.5 | |
|
3教科コース (英・数・国) |
11 | 320 | 120.5 |
118.1 (49.3) |
125.8 (51.6) |
-2.3 | 4,916 | 3,384 | 1,532 | 32.2 |
| 10 | 320 | 116.9 |
114.6 (49.3) |
121.8 (51.6) |
-2.3 | 4,913 | 3,372 | 1,541 | 31.2 | |
| 09 | 320 | 126.3 |
124.2 (49.5) |
130.8 (51.2) |
-1.7 | 5,288 | 3,563 | 1,725 | 38.1 | |
| 英語 | 11 | 120 | 55.7 |
54.6 (49.4) |
58.1 (51.4) |
-2.0 | 4,955 | 3,387 | 1,568 | 17.4 |
| 10 | 120 | 48.2 |
47.6 (49.6) |
49.4 (50.8) |
-1.2 | 4,995 | 3,387 | 1,568 | 15.8 | |
| 09 | 120 | 52.3 |
51.9 (49.8) |
53.0 (50.4) |
-0.6 | 5,331 | 3,578 | 1,753 | 16.6 | |
| 数学 | 11 | 80 | 24.4 |
23.8 (49.5) |
25.7 (51.0) |
-1.5 | 4,968 | 3,411 | 1,557 | 12.4 |
| 10 | 80 | 23.6 |
22.5 (49.2) |
26.2 (52.0) |
-2.8 | 4,963 | 3,396 | 1,567 | 13.3 | |
| 09 | 80 | 29.3 |
28.4 (49.5) |
31.4 (51.2) |
-1.7 | 5,355 | 3,594 | 1,761 | 17.2 | |
| 国語 | 11 | 120 | 40.2 |
39.6 (49.5) |
41.7 (51.3) |
-1.8 | 4,963 | 3,408 | 1,555 | 11.5 |
| 10 | 120 | 44.8 |
44.4 (49.5) |
45.9 (50.9) |
-1.4 | 4,957 | 3,396 | 1,561 | 10.6 | |
| 09 | 120 | 44.5 |
43.8 (49.5) |
45.8 (50.9) |
-1.4 | 5,356 | 3,596 | 1,760 | 14.0 | |
| 日本史 | 11 | 60 | 17.8 |
16.6 (48.5) |
20.6 (53.6) |
-5.1 | 2,827 | 1,942 | 885 | 7.7 |
| 10 | 60 | 18.8 |
17.1 (48.2) |
22.5 (54.0) |
-5.8 | 2,817 | 1,891 | 926 | 9.3 | |
| 09 | 60 | 21.1 |
19.5 (48.3) |
24.4 (53.6) |
-5.3 | 2,978 | 1,999 | 979 | 9.1 | |
| 世界史 | 11 | 60 | 18.4 |
16.7 (48.1) |
22.3 (54.4) |
-6.3 | 4,251 | 2,951 | 1,300 | 8.8 |
| 10 | 60 | 22.2 |
20.3 (48.3) |
26.7 (54.0) |
-5.7 | 4,219 | 2,945 | 1,274 | 11.3 | |
| 09 | 60 | 15.4 |
13.5 (48.1) |
19.4 (54.0) |
-5.9 | 4,569 | 3,127 | 1,442 | 9.9 | |
| 地理 | 11 | 60 | 17.8 |
16.7 (48.4) |
20.1 (53.4) |
-5.0 | 2,786 | 1,891 | 895 | 6.8 |
| 10 | 60 | 17.0 |
16.1 (48.8) |
18.8 (52.5) |
-3.7 | 2,856 | 1,926 | 930 | 7.2 | |
| 09 | 60 | 20.7 |
19.4 (48.3) |
23.1 (53.1) |
-4.8 | 3,061 | 2,003 | 1,058 | 7.7 | |
| 地歴2科目 | 11 | 120 | 36.2 |
33.3 (47.9) |
42.3 (54.5) |
-6.6 | 4,931 | 3,391 | 1,540 | 13.5 |
| 10 | 120 | 39.5 |
36.3 (48.1) |
46.2 (54.0) |
-5.9 | 4,945 | 3,380 | 1,565 | 16.6 | |
| 09 | 120 | 37.1 |
33.8 (47.9) |
43.9 (54.4) |
-6.5 | 5,302 | 3,563 | 1,739 | 15.5 | |
| 教科・コース | 年度 | 配点 | 平均点 |
偏差値現卒差 (現役-既卒) |
受検者数 | 標準偏差 | ||||
| 全体 | 現役 | 既卒 | 全体 | 現役 | 既卒 | |||||
|
4教科歴2コース (英・数・国・歴2) |
11 | 440 | 150.3 |
146.9 (49.3) |
157.2 (51.4) |
-2.1 | 8,722 | 5,829 | 2,893 | 48.9 |
| 10 | 440 |
132.9 |
129.4 (49.2) |
139.4 (51.5) |
-2.3 | 8,354 | 5,443 | 2,911 | 44.1 | |
| 09 | 440 |
137.7 |
133.4 (49.1) |
145.9 (51.7) |
-2.6 | 8,425 | 5,593 | 2,832 | 48.7 | |
|
3教科コース (英・数・国) |
11 | 320 | 116.7 |
115.7 (49.7) |
118.7 (50.5) |
-0.8 | 8,740 | 5,841 | 2,899 | 37.1 |
| 10 | 320 |
100.3 |
99.0 (49.6) |
102.6 (50.7) |
-1.1 | 8,367 | 5,450 | 2,917 | 33.3 | |
| 09 | 320 |
102.0 |
101.1 (49.8) |
103.7 (50.5) |
-0.7 | 8,450 | 5,607 | 2,843 | 34.7 | |
| 英語 | 11 | 120 | 51.2 |
50.8 (49.8) |
52.1 (50.5) |
-0.7 | 8,829 | 5,886 | 2,943 | 17.7 |
| 10 | 120 |
44.1 |
44.2 (50.1) |
44.0 (49.9) |
0.2 | 8,452 | 5,496 | 2,956 | 15.9 | |
| 09 | 120 |
47.4 |
47.2 (49.9) |
47.9 (50.3) |
-0.4 | 8,540 | 5,650 | 2,890 | 16.9 | |
| 数学 | 11 | 120 | 37.9 |
37.5 (49.8) |
38.6 (50.3) |
-0.5 | 8,873 | 5,908 | 2,965 | 20.3 |
| 10 | 120 |
27.7 |
26.5 (49.3) |
29.9 (51.3) |
-2.0 | 8,520 | 5,510 | 3,010 | 17.2 | |
| 09 | 120 |
29.4 |
28.7 (49.6) |
30.9 (50.8) |
-1.2 | 8,615 | 5,679 | 2,936 | 18.6 | |
| 国語 | 11 | 80 | 27.4 |
27.3 (49.9) |
27.6 (50.2) |
-0.3 | 8,811 | 5,874 | 2,937 | 8.6 |
| 10 | 80 |
28.2 |
28.2 (50.0) |
28.2 (50.0) |
0.0 | 8,460 | 5,482 | 2,978 | 8.2 | |
| 09 | 80 | 24.8 |
25.0 (50.2) |
24.4 (49.6) |
0.6 | 8,560 | 5,646 | 2,914 | 9.1 | |
| 物理 | 11 | 60 | 16.6 |
14.6 (48.1) |
20.6 (53.8) |
-5.7 | 7,868 | 5,277 | 2,591 | 10.6 |
| 10 | 60 |
17.0 |
16.0 (49.0) |
19.1 (52.2) |
-3.2 | 7,486 | 4,955 | 2,531 | 9.7 | |
| 09 | 60 |
19.5 |
17.7 (48.4) |
23.2 (53.3) |
-4.9 | 7,515 | 5,058 | 2,457 | 11.1 | |
| 化学 | 11 | 60 | 16.2 |
15.7 (49.3) |
17.3 (51.5) |
-2.2 | 8,740 | 5,848 | 2,892 | 7.3 |
| 10 | 60 |
15.1 |
14.0 (48.6) |
17.1 (52.6) |
-4.0 | 8,377 | 5,462 | 2,915 | 7.6 | |
| 09 | 60 |
15.6 |
14.1 (48.4) |
18.5 (53.0) |
-4.6 | 8,445 | 5,613 | 2,832 | 9.6 | |
| 生物 | 11 | 60 | 23.2 |
22.7 (49.5) |
24.1 (51.0) |
-1.5 | 1,005 | 629 | 376 | 9.1 |
| 10 | 60 |
20.0 |
18.9 (48.7) |
21.1 (51.4) |
-2.7 | 1,011 | 550 | 461 | 8.6 | |
| 09 | 60 |
22.0 |
20.2 (48.1) |
24.4 (52.5) |
-4.4 | 1,065 | 599 | 466 | 9.6 | |
| 地学 | 11 | 60 | 19.2 |
24.2 (53.6) |
17.5 (48.8) |
4.8 | 38 | 10 | 28 | 13.7 |
| 10 | 60 |
19.9 |
15.1 (46.0) |
23.2 (52.8) |
-6.8 | 36 | 15 | 21 | 12.0 | |
| 09 | 60 | 22.8 |
22.3 (49.6) |
23.1 (50.2) |
-0.6 | 37 | 14 | 23 | 12.2 | |
| 11 | 120 | 33.6 |
31.2 (48.4) |
38.4 (53.2) |
-4.8 | 8,825 | 5.882 | 2,943 | 15.2 | |
| 理科2科目 | 10 | 120 | 32.5 |
30.3 (48.5) |
36.6 (52.8) |
-4.3 | 8,455 | 5,491 | 2,964 | 14.5 |
| 09 | 120 | 35.4 |
32.1 (48.2) |
41.9 (53.6) |
-5.4 | 8,531 | 5,642 | 2,889 | 18.0 | |
09.19.12:38
2011/2012 東大入試実戦模試 第1回(8月)
中高一貫教育校の有名進学校をはじめ、ラ・サール高校255人(H23 254人)、鶴丸高校65人(H22 99人)が受験しています。
2011年度の東大合格者のうち81%(2479人)を実戦模試受験者が占めています。
2010/2011・2011/2012 東大入試実戦模試 第1回(8月)高校別受験者数
総受験者数13,565人 上段 平成23年度 下段 平成22年度
| 高校名 | 合計 | 高校名 | 合計 | 高校名 | 合計 |
| 開 成 |
455 439 |
盛岡第一 |
45 63 |
洛 星 |
27 37 |
| 麻 布 |
293 270 |
水戸第一 |
35 63 |
熊 本 |
41 37 |
| ラ・サール |
255 254 |
湘 南 |
66 63 |
お茶の水女子大 附属 |
23 36 |
| 駒場東邦 |
191 213 |
大分上野丘 |
58 63 |
弘 学 館 |
27 36 |
| 浦和(県立) |
199 209 |
雙 葉 |
46 60 |
秋 田 |
56 35 |
| 桜 陰 |
196 201 |
岡山白陵 |
69 60 |
仙台第二 |
53 33 |
| 東京学芸大附属 |
196 188 |
本郷(東京) |
56 59 |
東 葛 飾 |
31 33 |
| 栄光学園 |
181 188 |
高 崎 |
29 57 |
サレジオ学院 |
35 33 |
| 筑波大付属駒場 |
185 187 |
フェリス女学院 |
52 57 |
金沢泉丘 |
45 33 |
| 巣 鴨 |
195 180 |
芝 |
64 55 |
甲 府 南 |
33 |
| 海 城 |
177 171 |
前橋(県立) |
36 53 |
静 岡 |
30 33 |
| 日 比 谷 |
234 167 |
一 宮 |
49 53 |
柏 陽 |
32 |
| 灘 |
180 161 |
広島大付属福山 |
47 53 |
岡山朝日 |
43 32 |
| 桐蔭学園 |
135 157 |
甲陽学院 |
46 52 |
宮 崎 西 |
24 32 |
|
渋谷教育学園 幕張 |
213 149 |
高 松 |
49 52 |
川越(県立) |
30 |
|
聖光学院 (神奈川) |
154 145 |
東邦大付属東邦 |
102 51 |
國學院大久我山 |
26 30 |
| 筑波大付属 |
125 134 |
富 山 |
40 51 |
北 嶺 |
27 29 |
| 久留米大附設 |
114 123 |
藤 島 |
49 51 |
浦和第一女子 |
36 29 |
| 千葉(県立) |
111 111 |
山 形 東 |
40 50 |
岐 阜 |
41 29 |
| 愛 光 |
101 111 |
時 習 館 |
65 50 |
穎 明 館 |
39 28 |
| 宇 都 宮 |
86 108 |
修 猷 館 |
66 50 |
津 |
28 |
| 豊島岡女子学園 |
131 106 |
長野(県立) |
37 47 |
八王子東 |
27 27 |
| 土浦第一 |
125 105 |
国 立 |
54 45 |
公文国際学園 高等部 |
23 26 |
| 岡 崎 |
106 105 |
大阪星光学院 |
44 45 |
小 倉 |
23 26 |
| 桐 朋 |
102 104 |
智辯学園和歌山 |
28 45 |
船橋(県立) |
29 25 |
| 江戸川学園取手 |
82 103 |
広 島 学 院 |
68 45 |
鷗友学園女子 |
33 25 |
| 浅 野 |
100 102 |
札 幌 南 |
40 44 |
厚 木 |
25 |
| 東大寺学園 |
82 101 |
新 潟 |
59 44 |
沼 津 東 |
25 |
| 鶴 丸 |
65 99 |
浜 松 北 |
58 44 |
高 槻 |
25 |
| 武蔵(私立) |
97 96 |
長 崎 西 |
53 44 |
富士(静岡) |
27 24 |
| 女子学院 |
91 87 |
安 積 |
43 |
滝 |
38 24 |
| 西大和学園 |
69 84 |
桐 光 学 園 |
50 43 |
高田(6年生) |
33 24 |
| 城北(私立) |
85 81 |
高岡(富山) |
66 43 |
広島大附属 |
25 24 |
| 攻 玉 社 |
94 80 |
市川(千葉) |
43 42 |
札 幌 北 |
38 23 |
| 西(東京) |
80 79 |
暁 星 |
43 42 |
青 森 |
23 |
| 洛 南 |
63 78 |
白百合学園 |
39 42 |
膳 所 |
23 |
| 栄 東 |
81 75 |
四日市(三重) |
57 41 |
清 風 |
23 |
|
渋谷教育学園 渋谷 |
56 75 |
修 道 |
54 41 |
函館ラ・サール |
22 |
| 白 陵 |
129 75 |
開智(一貫部) |
35 40 |
武 生 |
22 |
| 青雲(長崎) |
83 74 |
世田谷学園 |
42 40 |
菊 里 |
22 |
| 横浜翠嵐 |
59 73 |
刈 谷 |
59 40 |
大阪桐蔭 |
22 |
| 旭丘(愛知) |
72 73 |
筑 紫 丘 |
32 40 |
白 鷗 |
21 |
| 東海(愛知) |
74 70 |
栃 木 |
39 |
松本深志 |
21 |
| 早 稲 田 |
70 67 |
戸 山 |
54 39 |
土 佐 |
30 21 |
| 富山中部 |
81 66 |
金沢大附属 |
37 39 |
宮崎大宮 |
29 21 |
| 大宮(埼玉) |
79 65 |
西武学園文理 |
29 37 |
||
| 2011年度 | |||||
| 佐賀西 | 36 | 高志(福井) | 29 | 開智(高等部S) | 25 |
| 海陽(中等教育) | 34 | 可児 | 29 | 昭和学院秀英 | 25 |
| 春日部 | 32 | 神戸女学院高等学部 | 27 | 宇都宮女子 | 23 |
| 八戸 | 29 | 長崎東 | 27 | 韮山 | 22 |
| 芝浦工業大学柏 | 29 | 逗子開成 | 26 | 佐世保北 | 22 |
09.17.21:54
2011/2012 東大入試実戦模試 第1回(8月)
東大入試実戦模試の結果が判明しましたので掲載します。
東大入試実戦模試の受験者数は、13,906人で昨年の13,565人に比較して341人増加しています。
東大入試実戦模試は、鹿児島県では公開会場がないため高校での受験等に限られ、鶴丸高校、ラ・サール高校等に限定されます。
2009/2010・2010/2011/2012東大模試(2009・2010・2011年実施)受験者数
| 模試名 | 模試主催者 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | ||
| 東大入試プレ | 代々木ゼミナール | 4,512 | - | 4,260(94.4) | ||
| 東大即応オープン | 河合塾 | 11,111 | 10,757 | 10,691(96.2) | 10,581(98.4) | |
| 東大入試実践 | 駿台予備校 | 14,091 | 12,895 | 13,565(96.3) | 12,718(98.6) | 13,906(102.5) |
09.16.19:01
鹿児島県内高校の国立大学合格実績
鹿児島県内私立高校国公立大学合格者数 ( )は公立大学で外数 【 】は鹿児島大で内数
| 高校名 |
主たる 学科 |
H19 | H20 | H21 | H22 | H23 |
| 鹿児島市内 | ||||||
|
池田学園 池田 |
普通科 | 34(2)【20】 | 35(4)【21】 | 32(2)【18】 | 33( 3)【25】 | 18(3)【8】 |
|
志学館 高等部 |
普通科 | 45(2)【13】 | 64(7)【26】 | 51(4)【22】 | 47( 3)【21】 | 41(1)【20】 |
| 樟南 | 普通科 | 29(0)【16】 | 59(9)【23】 | 85(5)【44】 | 50(16)【28】 | 74(17)【34】 |
| 鹿児島実業 | 文理科 | 34(6)【15】 | 47(7)【24】 | 23(10)【17】 | 24( 2)【12】 | 40(5)【26】 |
| 鹿児島 | 英数科 | 41(6)【25】 | 34(1)【20】 | 31(6)【20】 | 28( 3)【22】 | 21(5)【12】 |
|
鹿児島 修学館 |
普通科 | 11(1)【11】 | 16(2)【7】 | 14(3)【8】 | 19( 1)【11】 | 5(1)【4】 |
|
鹿児島 純心女子 |
普通科 | 17(0)【14】 | 16(3)【11】 | 14(4)【10】 | 14( 3)【10】 | 12(2)【8】 |
|
鹿児島 情報 |
プレ | 3(3)【 1】 | 11(10)【7】 | 17(6)【10】 | 20( 5)【12】 | 18(14)【6】 |
| 小計 | 214(20)【115】 | 282(43)【139】 | 267(40)【149】 | 235(36)【141】 | 229(45)【118】 | |
| 鹿児島市外 | ||||||
|
鹿児島 育英館 |
普通科 | 5(3)【 0】 | 6(1)【 2】 | 16(6)【 7】 | 6(2)【 4】 | 6(3)【2】 |
| 鹿児島第一 | 普通科 | 53(9)【16】 | 45(1)【26】 | 40(8)【15】 | 28(12)【12】 | 43(14)【22】 |
| 鹿屋中央 |
人間 科学科 |
1(0)【1】 | 1(0)【1】 | 0(0)【0】 | 0(1)【0】 | 4(2)【2】 |
|
神村学園 高等部 |
普通科 | 4(0)【1】 | 7(2)【1】 | 13(0)【9】 | 9(1)【3】 | 8(5)【3】 |
| 鳳凰 | 普通科 | 0(0)【0】 | 4(3)【1】 | 1(1)【0】 | 13(1)【3】 | 22(6)【6】 |
|
大口 明光学園 |
普通科 | 3(0)【0】 | 9(2)【4】 | 9(2)【4】 | 3(1)【1】 | 11(1)【4】 |
| 尚志館 | 特進科 | 14(10)【3】 | 18(9)【9】 | 17(5)【3】 | 19(4)【4】 | 27(5)【4】 |
| 出水中央 | 特進科 | 36(9)【13】 | 28(2)【14】 | 31(6)【9】 | 23(4)【6】 | 30(9)【7】 |
| 樟南第二 | 普通科 | 3(0)【2】 | 12(0)【4】 | 0(0)【0】 | 8(1)【4】 | 8(2)【3】 |
|
屋久島 おおぞら |
普通科 | 0(0)【0】 | 0(0)【0】 | 0(1)【0】 | 1(0)【0】 | 1(0)【0】 |
| れいめい | 文理科 | 32(0)【13】 | 24(2)【9】 | 23(4)【10】 | 23(3)【3】 | 22(2)【12】 |
| 小計 | 151(31)【49】 | 154(22)【71】 | 150(33)【58】 | 133(30)【41】 | 182(49)【65】 | |
| 合計 | 365(51)【164】 | 436(65)【210】 | 417(73)【207】 | 368(66)【182】 | 411(94)【183】 | |
|
ラ・サール 高校 |
150(10)【14】 | 193(10)【26】 | 180(3)【19】 | 142(4)【15】 |
鹿児島県内私立高校国立大学合格者数・現役進学(ラ・サール高校を含む)
| 区分 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | 備考 |
| 国立大学合格者数① | 586 | 610 | 548 | 553 | |||||||
| 国立大学現役進学者数② | 326 | 273 | 252 | 255 | 349 | 299 | 352 | 372 | 351 | ||
| ②-①(浪人者が主) | 236 | 238 | 197 |
平成14~22年度鹿児島県内高校の国立大現役進学者数 ( )は鹿児島県内国立大学で内数
| 年度 | 合計 | 普通科 |
農 業科 |
工業科 | 商業科 | 水産科 | その他 | 総合学科 |
家 庭 科 |
看 護 科 |
| H22 | 351(141) | 277(115) | - | 9(3) | 0 | - | 65(23) | 0 | 0 | 0 |
| H21 | 372(152) | 322(125) | - | 0 | 1(1) | - | 49(26) | 0 | 0 | 0 |
| H20 | 352(143) | 284(110) | - | 1(0) | 1(1) | - | 64(30) | 2(2) | 0 | 0 |
| H19 | 299(108) | 234( 76) | - | 1(0) | 1(1) | - | 63(31) | 0 | 0 | 0 |
| H18 | 349(137) | 284( 93) | - | 1(0) | 0 | - | 62(42) | 2(2) | 0 | 0 |
| H17 | 255( 98) | 223( 81) | - | 1(0) | 1(1) | - | 26(13) | 4(3) | 0 | 0 |
| H16 | 252( 91) | 214( 76) | - | 2(1) | 0 | - | 32(12) | 4(2) | 0 | 0 |
| H15 | 273( 97) | 229( 73) | - | 2(1) | 0 | - | 37(18) | 5(5) | 0 | 0 |
| H14 | 326(108) | 286( 84) | - | 1(1) | 3(2) | - | 33(20) | 3(1) | 0 | 0 |
09.15.19:48
鹿児島県内高校の国公立大学合格実績
18校の公立高校を除く国立大学の合格者数が公表されている公立高校は10校で、85人となっています。
鹿児島県高校の国立大学現役合格者数は平成21年度1852人、平成22年度1776人で、公立高校平成21年度1480人(79.9%)、平成22年度1425人(80.2%)、私立高校平成21年度372人(20.1%)、平成22年度351人(19.8%)となっています。
普通科を除く専門学科等から全体で平成21年度166人、平成22年度196人が国立大学に現役合格しており、公立高校から平成21年度116人、平成22年度74人、私立高校から平成21年度50人、平成22年度74人となっています。
鹿児島県内高校の国立大学合格実績
| 区 分 |
鹿 児 島 南 |
松 陽 |
開 陽 |
鹿 児 島 工 業 |
鹿 児 島 商 業 |
沖 永 良 部 |
鶴 翔 |
薩 摩 中 央 |
徳 之 島 |
中 種 子 ・ 種 子 島 中 央 |
屋 久 島 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
| H23年度 | 34 | - | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 6 | 13 | 92 | 21 | 142 |
| H22年度 | 29 | - | 6 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 15 | 85 | 28 | 180 |
平成21・22年度鹿児島県内高校の国立大現役進学者数
| 高校 | 大学 | 合計 | 普通科 | 農業科 | 工業科 | 商業科 | 水産科 | その他 | 総合学科 | 家庭科 | 看護科 |
|
公立 ・私立 |
国立大合計 |
1776 1852 |
1580 1686 |
7 9 |
18 11 |
20 15 |
0 2 |
138 124 |
9 5 |
4 0 |
0 0 |
| 県内国立大 |
804 812 |
731 740 |
7 9 |
6 4 |
4 8 |
0 1 |
52 49 |
3 1 |
1 0 |
0 0 |
|
| 県外国立大 |
972 1040 |
849 946 |
0 0 |
12 7 |
16 7 |
0 1 |
86 75 |
6 4 |
3 0 |
0 0 |
|
| 公立 | 国立大合計 |
1425 1480 |
1303 1364 |
7 9 |
9 11 |
20 14 |
0 2 |
73 75 |
9 5 |
4 0 |
0 0 |
| 県内国立大 |
663 660 |
616 615 |
7 9 |
3 4 |
4 7 |
0 1 |
29 23 |
3 1 |
1 0 |
0 0 |
|
| 県外国立大 |
762 820 |
687 749 |
0 0 |
6 7 |
16 7 |
0 1 |
44 52 |
6 4 |
3 0 |
0 0 |
|
| 私立 | 国立大合計 |
351 372 |
277 322 |
- - |
9 0 |
0 1 |
- - |
65 49 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 県内国立大 |
141 152 |
115 125 |
- - |
3 0 |
0 1 |
- - |
23 26 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 県外国立大 |
210 220 |
162 197 |
- - |
6 0 |
0 0 |
- - |
42 23 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
平成22・23年度の鹿児島県内私立高校の国立大学合格実績
| 区 分 |
志 学 館 |
池 田 |
樟 南 |
鹿 児 島 実 |
鹿 児 島 修 学 館 |
鹿 児 島 純 心 |
鹿 児 島 情 報 |
神 村 学 園 |
鹿 児 島 育 英 館 |
れ い め い |
出 水 中 央 |
鳳 凰 |
鹿 児 島 第 一 |
尚 志 館 |
大 口 明 光 |
鹿 屋 中 央 |
樟 南 第 二 |
加 治 木 女 子 |
鹿 児 島 城 西 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
| H23年度 | 41 | 18 | 74 | 40 | 5 | 12 | 18 | 8 | 6 | 22 | 30 | 22 | 43 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 21 | 142 |
| H22年度 | 47 | 33 | 50 | 24 | 19 | 14 | 20 | 9 | 6 | 22 | 23 | 13 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 28 | 180 |
09.14.22:52
鹿児島県内高校の国立大学合格実績
昭和50年度の国立大学入試制度は、1期校、2期校に区分されており、現在の入試制度と異なりますが、ここでは単純比較してみます。
鹿児島県内の公立高校18校の国立大学合格実績数は、昭和50年度の1967人に対して平成22年度は1558人となっており、79.2%、平成23年度は1536人で78.1%の割合となっています。
なお、ここで国分高校の国立大学合格者数のみのデータが公表されていないため、国公立大学合格者数を掲載しています。
平成22年度の公立高校の国立大学合格者数1558人と鹿児島高校・ラ・サール高校を除く私立高校の国立大学合格者数330人の合計は、1888人となります。
平成22年度の国立大学合格者数1888人は、昭和50年度の公立高校18校の合格者数1967人(鹿児島高校を除く私立高校の国立大学実績はないものと仮定)に対して96.0%となっています。
平成23年度の公立高校の国立大学合格者数1536人と鹿児島高校・ラ・サール高校を除く私立高校の国立大学合格者数377人の合計は、1913人となります。
平成23年度の国立大学合格者数1913人は、昭和50年度の公立高校18校の合格者数1967人(鹿児島高校を除く私立高校の国立大学実績はないものと仮定)に対して97.3%となっています。
公立高校18校の国立大学合格者数の減少分は、私立高校の増加分でほぼカバーしていることとなります。
鹿児島県内高校の国立大学合格実績
| 区 分 |
鶴 丸 |
甲 南 |
中 央 |
鹿 屋 |
玉 龍 |
錦 江 湾 |
加 治 木 |
川 内 |
出 水 |
加 世 田 |
国 分 |
宿 |
志 布 志 |
大 島 |
川 辺 |
大 口 |
伊 集 院 |
種 子 島 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
| H23年度 | 241 | 243 | 174 | 107 | 89 | 28 | 158 | 116 | 41 | 82 | ※65 | 25 | 27 | 53 | 16 | 12 | 40 | 19 | 1536 | 21 | 142 |
| H22年度 | 221 | 242 | 188 | 97 | 115 | 20 | 166 | 133 | 48 | 61 | *59 | 40 | 19 | 50 | 24 | 8 | 51 | 16 | 1558 | 28 | 180 |
| S50年度 | 346 | 311 | 290 | 161 | 108 | 104 | 88 | 86 | 73 | 72 | 58 | 52 | 42 | 42 | 40 | 36 | 34 | 24 | 1967 | 18 | 208 |
| 対比% | 64 | 79 | 66 | 61 | 106 | 25 | 190 | 155 | 66 | 88 | - | 77 | 45 | 119 | 60 | 22 | 150 | 71 | 80.4 | 156 | 87 |
平成22年度の鹿児島県内私立高校の国立大学合格実績
| 年度 |
志 学 館 |
池 田 |
樟 南 |
鹿 児 島 実 |
鹿 児 島 修 学 館 |
鹿 児 島 純 心 |
鹿 児 島 情 報 |
神 村 学 園 |
鹿 児 島 育 英 館 |
れ い め い |
出 水 中 央 |
鳳 凰 |
鹿 児 島 第 一 |
尚 志 館 |
大 口 明 光 |
鹿 屋 中 央 |
樟 南 第 二 |
加 治 木 女 子 |
鹿 児 島 城 西 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
| H23 | 41 | 18 | 74 | 40 | 5 | 12 | 18 | 8 | 6 | 22 | 30 | 22 | 43 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 21 | 142 |
| H22 | 47 | 33 | 50 | 24 | 19 | 14 | 20 | 9 | 6 | 22 | 23 | 13 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 28 | 180 |
09.13.23:26
鹿児島県内高校の国公立大学合格実績
減少した理由のひとつは、入学定員数が減少したこととと私立高校の台頭が考えられます。
そこで、今回は私立高校の難関国立大学の合格実績を加えて分析してみます。
さらに、国公立大学医学部の合格者数を加えます。
平成22・23年度の昭和50年度に合格実績があった鹿児島高校・ラ・サール高校を除く私立高校の難関国立大の合格者数は平成22年度34人、平成23年度49人、国公立大医学部は平成22年度35人、平成23年度22人となっており、全体で平成22年度69人、平成23年度71人が合格しています。
この平成22・23年度の私立高校の合格実績69人、71人と18の公立高校の難関国立大学合格者数171人、194人を足すと平成22年度240人、平成23年度265人となります。
つまり、全体では、昭和50年度の334人と平成22年度の240人、平成23年度265人の比率を求めると、平成22年度71.9%、平成23年度79.3%となります。
鹿児島県内の高校の卒業生数が昭和55年度に対して平成22年度は60%程度となっていますが、公立・私立高校を合わせて考えると国立難関大学の合格者数は60%まで低下することなく、71.9%、79.3%を維持しています。
したがって、公立高校18校と鹿児島高校・ラサール高校を除く私立高校の難関国立大学合格者数だけをみると、21~28%程度減少しており、これが鹿児島県内の高校の進学実績の低下として評価されがちですが、減少率からみると高校卒業生の減少率40%より小さいため、難関国立大学の合格者数は10%~20%伸びているものと思われます。
全体的に言えることは、私立高校の台頭によって公立高校全体の進学実績の低下につながっているように見えますが、逆にいうと私立高校によって鹿児島県内の難関大学の合格実績が維持・向上しているとも言えます。
また、鶴丸高校の難関国立大学の合格者数は、昭和50年に対して77%~79%となっており、卒業生数の60%より20%程度高い水準にあるものの、甲南、鹿児島中央は合格者数の低下割合が大きく、このことは鹿児島市内の私立高校への学生流出の影響を受けていると思われます。
なお、鶴丸高校の難関大学の合格者が昭和50年度に比較して80%程度で高いのは、浪人生の増加によって確保されているのではないかとも思われますので、これについては今後分析したいと思います。
平成22・23年度の鹿児島県内私立高校の難関国立大学9大学・医学部の国立大学合格実績
| 区 分 |
年 度 |
志 学 館 |
池 田 |
樟 南 |
鹿 児 島 実 |
鹿 児 島 修 学 館 |
鹿 児 島 純 心 |
鹿 児 島 情 報 |
神 村 学 園 |
鹿 児 島 育 英 館 |
れ い め い |
出 水 中 央 |
鳳 凰 |
鹿 児 島 第 一 |
尚 志 館 |
大 口 明 光 |
鹿 屋 中 央 |
樟 南 第 二 |
加 治 木 女 子 |
鹿 児 島 城 西 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
| 難関大 | H23 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 3 | 74 |
| H22 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 94 | |
| 国公立大医学部 | H23 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 69 |
| H22 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 89 | |
| 小 計 | H23 | 19 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 3 | 143 |
| H22 | 24 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 183 |
鹿児島県内高校の難関国立大学9大学国立大学合格実績
| 区 分 |
鶴 丸 |
甲 南 |
中 央 |
鹿 屋 |
玉 龍 |
錦 江 湾 |
加 治 木 |
川 内 |
出 水 |
加 世 田 |
国 分 |
指 宿 |
志 布 志 |
大 島 |
川 辺 |
大 口 |
伊 集 院 |
種 子 島 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
| H23年度 | 98 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | 3 | 74 |
| H22年度 | 96 | 35 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 1 | 94 |
| S50年度 | 124 | 66 | 48 | 20 | 4 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 334 | 3 | 134 |
| H23対S50比% | 79 | 67 | 21 | 40 | 50 | 0 | 109 | 45 | 60 | 75 | 0 | 50 | - | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 58.1 | 100 | 55 |
| H22対S50比% | 77 | 53 | 10 | 25 | 75 | 0 | 118 | 55 | 40 | 13 | 33 | 0 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | - | 51.2 | 33 | 70 |
| 平均S50比% | 78 | 60 | 16 | 33 | 63 | 0 | 114 | 50 | 50 | 44 | 17 | 25 | - | 75 | 0 | 0 | 17 | 0 | 54.6 | 67 | 63 |
09.12.19:41
鹿児島県内高校の国立大学合格実績
比較対象の合格実績数は、昭和50年度のデータがある鶴丸、甲南、鹿児島中央、錦江湾、玉龍、鹿屋、志布志、加治木、大口、出水、川内、伊集院、加世田、国分、川辺、指宿、種子島、大島の18校の合計数で見てみます。
難関国立大学(旧帝大+一橋大+東工大)9大学の合格実績を比較します。
17校の全体では、昭和50年度の334人に対して平成22年度は171人と51.2%、平成23年度は194人と58.1%に低下しています。
各高校別にみると、昭和50年度の合格実績を2カ年とも上回っているのは、18高校の中で加治木高校だけです。定員が平均で昭和50年度の60%程度となっていることから、加治木高校は実質平均学力が伸びているものと想定されます。
平成22・23年の各高校の卒業生数を鶴丸高校と同様、昭和50年の60%程度と想定した場合、国立大学の定員数は変動があるものの、昭和55年度と平成22・23年度の定員数はほとんど変わらないと考えられることから、合格者数が昭和50年度の60%に満たない場合は、平均学力が低下し、合格者数も実質低下したものと想定されます。
2カ年の合格者数の平均が60%を下回っているのは、中央、鹿屋、川内、出水、加世田、国分の他に錦江湾、指宿、志布志、川辺、伊集院は実績0となっています。
特に、中央、錦江湾、鹿屋、加世田、川辺の減少が目立ちます。
減少の大きな要因は、九大の合格者数が減少したことにあります。
(九大)
中央 45 → H22 5、H23 9 錦江湾 5 →H22・23 0 鹿屋 18 →H22 3、H23 4
川辺 7 → H22・H23 0
ラ・サール高校は、東大から国公立大学医学部にシフトしているため、一概には言えませんが難関国立大学の合格実績は昭和50年度の55%~70%程度となっています。
鹿児島県内高校の難関国立大学9大学国立大学合格実績
| 区 分 |
鶴 丸 |
甲 南 |
中 央 |
鹿 屋 |
玉 龍 |
錦 江 湾 |
加 治 木 |
川 内 |
出 水 |
加 世 田 |
国 分 |
指 宿 |
志 布 志 |
大 島 |
川 辺 |
大 口 |
伊 集 院 |
種 子 島 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
| H23年度 | 98 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | 3 | 74 |
| H22年度 | 96 | 35 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 171 | 1 | 94 |
| S50年度 | 124 | 66 | 48 | 20 | 4 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 334 | 3 | 134 |
| H23対S50比% | 79 | 67 | 21 | 40 | 50 | 0 | 109 | 45 | 60 | 75 | 0 | 50 | - | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 58.1 | 100 | 55 |
| H22対S50比% | 77 | 53 | 10 | 25 | 75 | 0 | 118 | 55 | 40 | 13 | 33 | 0 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | - | 51.2 | 33 | 70 |
| 平均S50比% | 78 | 60 | 16 | 33 | 63 | 0 | 114 | 50 | 50 | 44 | 17 | 25 | - | 75 | 0 | 0 | 17 | 0 | 54.6 | 67 | 63 |
09.11.11:32
鹿児島県内高校の国立大学合格実績
国分高校は、国立大学の合格実績が公表されていません。
分析結果については、明日掲載したいと思います。
平成22・23年度鹿児島県内高校の国立大学合格実績 上段:平成23年度 下段:平成22年度
|
鶴 丸 |
甲 南 |
中 央 |
鹿 屋 |
玉 龍 |
錦 江 湾 |
加 治 木 |
川 内 |
出 水 |
加 世 田 |
国 分 |
指 宿 |
志 布 志 |
大 島 |
川 辺 |
大 口 |
伊 集 院 |
種 子 島 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
|
| 東大 |
25 15 |
1 |
26 15 |
29 36 |
|||||||||||||||||
| 京大 |
6 4 |
4 3 |
1 |
1 |
10 9 |
8 4 |
|||||||||||||||
| 九大 |
37 48 |
29 26 |
9 5 |
4 3 |
2 2 |
7 10 |
5 5 |
2 2 |
5 1 |
2 |
1 |
4 1 |
1 |
1 |
106 106 |
1 1 |
20 26 |
||||
| 北大 |
1 |
1 2 |
1 |
3 2 |
1 4 |
||||||||||||||||
| 東北大 |
4 3 |
2 1 |
1 |
6 5 |
1 12 |
||||||||||||||||
| 名大 |
3 2 |
1 |
1 |
4 3 |
5 3 |
||||||||||||||||
| 阪大 |
14 15 |
6 |
1 |
2 1 |
1 |
2 2 |
1 |
1 |
1 |
27 20 |
2 |
2 5 |
|||||||||
| 小計 |
90 87 |
43 33 |
10 5 |
7 5 |
2 3 |
0 |
10 13 |
5 6 |
3 2 |
6 1 |
2 |
1 |
0 |
4 2 |
0 |
0 |
1 0 |
1 |
182 160 |
3 1 |
66 90 |
| 一橋大 |
4 7 |
2 |
1 |
1 |
6 9 |
6 3 |
|||||||||||||||
| 東工大 |
4 2 |
1 |
1 |
6 2 |
2 1 |
||||||||||||||||
| 小計 |
8 9 |
1 2 |
1 |
2 |
12 11 |
8 4 |
|||||||||||||||
| 合計 |
98 96 |
44 35 |
10 5 |
8 5 |
2 3 |
0 |
12 13 |
5 6 |
3 2 |
6 1 |
2 |
1 |
0 |
4 2 |
0 |
0 |
1 0 |
1 |
194 171 |
3 1 |
74 94 |
| 筑波大 |
4 2 |
4 5 |
1 |
7 |
1 |
3 4 |
2 1 |
2 |
2 |
1 |
23 16 |
4 2 |
|||||||||
| 東京外大 |
3 1 |
1 1 |
1 |
1 |
1 |
7 2 |
1 1 |
||||||||||||||
| 東京学芸大 |
5 1 |
4 4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 1 |
1 |
2 1 |
1 |
15 12 |
||||||||||
| 東京農工大 |
4 2 |
1 |
1 |
6 2 |
2 1 |
||||||||||||||||
| お茶の水女子大 |
5 4 |
1 2 |
6 6 |
||||||||||||||||||
| 電気通信大 |
1 1 |
1 2 |
1 |
2 4 |
1 |
||||||||||||||||
| 横浜国立大 |
7 4 |
2 4 |
3 2 |
1 |
4 1 |
17 11 |
5 9 |
||||||||||||||
| 大阪外語大 | |||||||||||||||||||||
| 奈良女子大 |
3 2 |
2 |
1 1 |
1 |
1 |
1 |
9 3 |
||||||||||||||
| 広島大 |
9 12 |
9 12 |
8 6 |
3 1 |
1 3 |
6 11 |
5 5 |
2 1 |
4 3 |
1 |
5 1 |
1 |
54 55 |
1 |
1 2 |
||||||
| 九州工業大 |
2 1 |
4 9 |
5 6 |
5 3 |
3 4 |
1 1 |
6 3 |
2 1 |
3 3 |
2 2 |
1 |
1 |
1 |
34 35 |
1 |
2 |
|||||
| 佐賀大 |
|
1 1 |
2 1 |
2 2 |
1 1 |
2 1 |
4 5 |
2 7 |
2 5 |
2 2 |
2 |
2 1 |
1 2 |
1 |
22 30 |
1 |
3 2 |
||||
| 長崎大 |
1 |
10 3 |
1 3 |
4 6 |
6 6 |
2 1 |
3 5 |
6 3 |
3 |
2 1 |
1 2 |
2 |
2 2 |
1 |
1 1 |
40 38 |
1 |
3 3 |
|||
| 熊本大 |
5 12 |
20 18 |
15 15 |
8 10 |
4 5 |
1 |
21 26 |
9 15 |
3 4 |
4 4 |
1 1 |
1 1 |
3 1 |
1 |
1 |
2 6 |
1 |
100 118 |
2 |
7 11 |
|
| 大分大 |
1 |
1 4 |
1 |
3 |
2 2 |
2 |
2 |
2 |
1 4 |
1 |
2 |
1 |
5 |
1 1 |
1 3 |
3 1 |
15 28 |
1 |
1 |
||
| 宮崎大 |
1 1 |
5 8 |
7 1 |
12 6 |
2 6 |
2 5 |
9 6 |
6 13 |
1 1 |
6 7 |
2 5 |
3 4 |
6 1 |
2 5 |
2 |
3 6 |
1 |
68 77 |
2 |
5 4 |
|
| 鹿児島大 |
74 70 |
119 112 |
111 123 |
51 48 |
54 64 |
14 8 |
71 65 |
61 60 |
19 21 |
37 29 |
15 18 |
12 5 |
15 11 |
9 9 |
6 |
25 25 |
12 8 |
705 676 |
12 22 |
15 19 |
|
| 琉球大 |
1 |
3 1 |
3 2 |
1 |
1 3 |
2 |
2 1 |
1 4 |
2 |
1 |
7 6 |
2 1 |
1 |
1 |
1 1 |
23 29 |
1 |
||||
| 小計 |
124 113 |
184 184 |
155 161 |
98 80 |
78 97 |
25 20 |
130 144 |
89 108 |
29 38 |
66 58 |
23 28 |
22 12 |
40 26 |
14 22 |
8 4 |
36 42 |
19 12 |
1139 1149 |
20 27 |
47 57 |
|
| その他 |
19 12 |
16 23 |
19 24 |
1 12 |
9 18 |
2 |
16 23 |
22 19 |
9 8 |
10 2 |
1 12 |
5 7 |
9 12 |
2 2 |
4 4 |
4 9 |
4 |
148 191 |
1 1 |
21 29 |
|
| 国立大 |
241 221 |
243 242 |
174 188 |
107 97 |
89 115 |
28 20 |
158 166 |
116 133 |
41 48 |
82 61 |
(65) (59) |
25 40 |
27 19 |
53 50 |
16 24 |
12 8 |
40 51 |
19 16 |
1471 1499 |
21 28 |
142 180 |
09.10.07:28
昭和50年度の鹿児島県内高校の国立大学合格者数
現在の国立大学の合格実績との比較を行うためには、各種要素を調べておく必要があります。
①鹿児島県内高校の在校生数数と鶴丸高校の卒業生数
平成21年の鹿児島県の高校の在校生数は、昭和50年に比較して58.1%となっています。
また、平成21年の鶴丸高校の卒業生数は、昭和50年に比較して62.5%となっています。
このことから、鹿児島県内の学生数を考慮して定員を減少させており、各高校ともほぼどうような割合で卒業数が減少しているものと想定されます。
②東京大学の入学定員と全国の高校卒業生数・大学進学率
平成21年度の東大の入学定員は、昭和54年度と同数となっています。東大の入学定員は、平成4年度には3586人まで増員され、その後、減少しています。
平成21年の全国の高校卒業生は、昭和50年に比較して80.1%となっていますが、大学の進学率は26.7%から50.2%に上昇しています。
難関大学レベルにある生徒は、ほぼ100%大学に進学するものと想定され、大学進学率は考慮する必要性はそれほど高くないと思われます。
この2つのことから、鹿児島県の卒業生数や在校生数の昭和50年に対する割合が60%に落ち込んでいるのに対して、全国平均は80%程度にとどまっていることから、鹿児島県の高校の卒業生の全国の卒業生に対する割合が低下することとなり、難関大学の国立大学合格者数は昭和50年の60%以下になることが推測されます。
たとえば、九大であれば、卒業生数の割合から鹿児島県の合格者数が60%以下となり、福岡県等の合格者数は増加するということになります。
したがって、よく鹿児島県の高校の学力が低下したとよく言われますが、上記のような卒業生数の減少傾向が他県に比較して大きいことが合格者数の減少につながり、合格者数だけで見ている場合が多くあるのではないかと思われます。
| 区 分 | 昭和50年① | 平成21年② | 割合②/①(%) | 備 考 |
|
鹿児島県内 全日制本科学生数(公立・私立)3学年合計 (1学年平均生徒数) |
90,498 (30,166) |
52,535 (17,512) |
58.1 | |
| 全国高校卒業生数 | 1,327,407 | 1,063,581 | 80.1 | |
| 鶴丸高校卒業生数 | 496 | 310 | 62.5 | |
| 東京大学入学定員 | ※3,063 | 3,063 | 100.0 | |
| 全国4年制大学進学率 | 27.2% | 50.2% | 188.0 |
09.07.18:37
昭和50年度鹿児島県内高校の国公立大学合格実績
しかし、これは、いつの時代との比較でそのような話になっているか具体的なデータで検証したものは見受けられません。
そこで、今回は、過去の文献から検証してみたいと思います。このデータは昨年10月にも掲載させて頂きましたが今一度確認したいと思います。
鹿児島県の主な高校の合格実績は、過去の情報はサンデー毎日や週刊朝日などの週刊誌に掲載されていますが、現在そのような雑誌は手元にありません。
そこで、今回は、過去のデータで唯一書籍で掲載されている昭和50年度の国立大学の合格実績について掲載します。
鶴丸高校等の大規模校の卒業生数は500人前後で現在より1.56倍多くなっています。
公立高校18校の九大合格者は246人に達しています。
鹿屋高校の九大合格者数18人が目を引きます。また、多くの高校(少なくとも16校)が九大に合格者を出していることがわかります。
昭和50年度鹿児島県内高校の国立大学合格実績
|
鶴 丸 |
甲 南 |
中 央 |
鹿 屋 |
玉 龍 |
錦 江 湾 |
加 治 木 |
川 内 |
出 水 |
加 世 田 |
国 分 |
指 宿 |
志 布 志 |
大 島 |
川 辺 |
大 口 |
伊 集 院 |
種 子 島 |
小 計 |
鹿 児 島 |
ラ ・ サ ー ル |
|
| 東大 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 83 | ||||||||||||
| 京大 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 | ||||||||||||
| 九大 | 85 | 49 | 44 | 18 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 246 | 2 | 29 | ||
| 北大 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 東北大 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 名大 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 阪大 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 小計 | 114 | 65 | 47 | 20 | 4 | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 318 | 3 | 134 | ||
| 一橋大 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 東工大 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 小計 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 合計 | 124 | 66 | 48 | 20 | 4 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 334 | 146 | |||
| 筑波大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 東京外大 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 東京農工大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| お茶の水女子大 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 電気通信大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 横浜国立大 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 大阪外語大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 奈良女子大 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 広島大 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 38 | 1 | |||||||||||
| 九州工業大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 佐賀大 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 1 | |||||||||
| 長崎大 | 21 | 4 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | |||||
| 熊本大 | 21 | 30 | 12 | 11 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 139 | 1 | 11 | ||
| 大分大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
| 宮崎大 | 4 | 17 | 33 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 15 | 7 | 10 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 169 | ||
| 鹿児島大 | 111 | 146 | 149 | 55 | 55 | 57 | 42 | 32 | 19 | 30 | 25 | 25 | 15 | 14 | 12 | 11 | 18 | 7 | 823 | 9 | 21 |
| 琉球大 | 1 | 6 | 20 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 | 2 | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 115 | 3 | ||||
| 小計 | 208 | 221 | 230 | 128 | 89 | 86 | 73 | 67 | 56 | 58 | 50 | 49 | 39 | 32 | 31 | 25 | 29 | 22 | 1493 | 14 | 46 |
| その他 | 14 | 24 | 12 | 13 | 15 | 6 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 140 | 1 | 16 |
| 国立大 | 346 | 311 | 290 | 161 | 108 | 104 | 88 | 86 | 73 | 72 | 58 | 52 | 42 | 42 | 40 | 36 | 34 | 24 | 1967 | 18 | 208 |