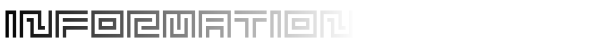カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
カテゴリー
ブログの目次
フリーエリア
最新コメント
[09/25 匿名希望]
[07/08 保護者]
[03/15 気を揉む母]
[04/17 パパ]
[04/10 あ]
[04/04 あ]
[03/05 受験生の親]
[03/03 NONAME]
[01/24 あ]
[01/21 あ]
[12/22 チェスター]
[07/09 NONAME]
[05/31 NONAME]
[03/22 NONAME]
[03/18 NONAME]
[03/17 NONAME]
[03/10 NONAME]
[03/07 NONAME]
[03/05 NONAME]
[02/15 チェスター]
[02/10 受験母]
[01/22 あ]
[12/07 2022公立高校]
[11/23 NONAME]
[08/28 NONAME]
最新記事
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(06/17)
(05/09)
(03/13)
(02/15)
(07/10)
(06/20)
(05/19)
(05/04)
(04/25)
(03/11)
(02/28)
(02/15)
(05/13)
(05/10)
(04/23)
(04/18)
(04/16)
(03/12)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
教育に関心を持つサラリーマン
性別:
男性
自己紹介:
高校教育・高校入試に関心を持つ親です。
情報交換が楽しみです。
情報交換が楽しみです。
バーコード
RSS
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(05/09)
(05/09)
(05/10)
(05/10)
(05/10)
(05/10)
(05/10)
(05/11)
(05/11)
(05/11)
(05/11)
(05/11)
(05/12)
(05/13)
(05/13)
(05/14)
(05/15)
(05/16)
(05/17)
(05/17)
(05/17)
(05/18)
(05/18)
(05/19)
(05/20)
お天気情報
-天気予報-
カウンター
FX NEWS
-外国為替-
アクセス解析
12.05.09:05
[PR]
05.18.20:03
東京大学入試状況
「何点落とせるか」の”下限ライン”を設定する
以上のように、本書では780点(文Ⅰは800点、理Ⅲは820点)を”戦略的な目標点”として設定するが、本番では思わぬ失敗をして目標を下回ることもあるだろう。問題はその場合、どこで踏みとどまれば2次で逆転のチャンスがあるかだが、これは「目標-40点」の740点(文Ⅰは760点、理Ⅲは780点)と考えたい。
前述の通り、センター試験では740点を超えれば、理Ⅲを除いて第一次段階選抜にかかることは基本的にない。ちなみに理Ⅲの780点は平成18年度の第一次段階選抜ライン(797点)、文Ⅲと理Ⅰの740点は平成20年度の同ライン(文Ⅲ748点、理Ⅰ749点)を下回るが、これは極端な例外と考えて差し支えない。
目標得点との40点差は、2次試験に換算すると約4.9点になる。この程度の差なら、2次試験の頑張りで充分に挽回可能である。実際、2次試験本番では、たとえばその日の体調や問題傾向によって20~30点くらいはすぐに上下動する(だからこそ、「試験は水物」と言われるのであるが)。
そこで、”第1目標”としては780点(文Ⅰは800点、理Ⅲは820点)を掲げておくが、この目標に達しない場合を想定した”下限ライン”を740点(文Ⅰは760点、理Ⅲは780点)とした上で、各科目で「何点まで落とせるか」を想定して、それぞれ「マイナス10点までは可」のように振り振っておく。何のためにそんなことをするかというと、失敗したときの”精神的ダメージ”を最小限に食い止めるためでもある。
たとえば、最初の試験科目でちょっとした失敗をすると、精神的に動揺して、あとの試験に悪影響を及ぼすことが往々にしてある。しかし、あらかじめ「このくらいは落としても大丈夫」というラインを科目ごとに設定しておけば、開き直って試験を受けることができるし、ちょっとした失敗から立ち直るのも早い。
以上のように、本書では780点(文Ⅰは800点、理Ⅲは820点)を”戦略的な目標点”として設定するが、本番では思わぬ失敗をして目標を下回ることもあるだろう。問題はその場合、どこで踏みとどまれば2次で逆転のチャンスがあるかだが、これは「目標-40点」の740点(文Ⅰは760点、理Ⅲは780点)と考えたい。
前述の通り、センター試験では740点を超えれば、理Ⅲを除いて第一次段階選抜にかかることは基本的にない。ちなみに理Ⅲの780点は平成18年度の第一次段階選抜ライン(797点)、文Ⅲと理Ⅰの740点は平成20年度の同ライン(文Ⅲ748点、理Ⅰ749点)を下回るが、これは極端な例外と考えて差し支えない。
目標得点との40点差は、2次試験に換算すると約4.9点になる。この程度の差なら、2次試験の頑張りで充分に挽回可能である。実際、2次試験本番では、たとえばその日の体調や問題傾向によって20~30点くらいはすぐに上下動する(だからこそ、「試験は水物」と言われるのであるが)。
そこで、”第1目標”としては780点(文Ⅰは800点、理Ⅲは820点)を掲げておくが、この目標に達しない場合を想定した”下限ライン”を740点(文Ⅰは760点、理Ⅲは780点)とした上で、各科目で「何点まで落とせるか」を想定して、それぞれ「マイナス10点までは可」のように振り振っておく。何のためにそんなことをするかというと、失敗したときの”精神的ダメージ”を最小限に食い止めるためでもある。
たとえば、最初の試験科目でちょっとした失敗をすると、精神的に動揺して、あとの試験に悪影響を及ぼすことが往々にしてある。しかし、あらかじめ「このくらいは落としても大丈夫」というラインを科目ごとに設定しておけば、開き直って試験を受けることができるし、ちょっとした失敗から立ち直るのも早い。
PR
- 05/18/20:03
- 平成22年度大学入試
- コメント:0
- トラックバック:
- トラックバックURLはこちら