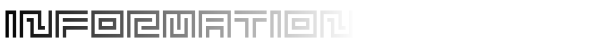カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
カテゴリー
ブログの目次
フリーエリア
最新コメント
[09/25 匿名希望]
[07/08 保護者]
[03/15 気を揉む母]
[04/17 パパ]
[04/10 あ]
[04/04 あ]
[03/05 受験生の親]
[03/03 NONAME]
[01/24 あ]
[01/21 あ]
[12/22 チェスター]
[07/09 NONAME]
[05/31 NONAME]
[03/22 NONAME]
[03/18 NONAME]
[03/17 NONAME]
[03/10 NONAME]
[03/07 NONAME]
[03/05 NONAME]
[02/15 チェスター]
[02/10 受験母]
[01/22 あ]
[12/07 2022公立高校]
[11/23 NONAME]
[08/28 NONAME]
最新記事
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(12/31)
(06/17)
(05/09)
(03/13)
(02/15)
(07/10)
(06/20)
(05/19)
(05/04)
(04/25)
(03/11)
(02/28)
(02/15)
(05/13)
(05/10)
(04/23)
(04/18)
(04/16)
(03/12)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
教育に関心を持つサラリーマン
性別:
男性
自己紹介:
高校教育・高校入試に関心を持つ親です。
情報交換が楽しみです。
情報交換が楽しみです。
バーコード
RSS
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(05/09)
(05/09)
(05/10)
(05/10)
(05/10)
(05/10)
(05/10)
(05/11)
(05/11)
(05/11)
(05/11)
(05/11)
(05/12)
(05/13)
(05/13)
(05/14)
(05/15)
(05/16)
(05/17)
(05/17)
(05/17)
(05/18)
(05/18)
(05/19)
(05/20)
お天気情報
-天気予報-
カウンター
FX NEWS
-外国為替-
アクセス解析
12.09.12:20
[PR]
05.23.23:07
東京大学入試状況
東京大学入試状況について掲載します。
コストパフォーマンスを考えた「現実的な目標設定」が命
科目別の目標得点を設定するときには、「悪くてもこのぐらい」という発想は重要だ。「やれば伸びるだろう」という”希望的観測”だけでむやみに目標ラインを上に設定しないほうがよい。
2次試験では、たとえば文系の国語で96点(80%)以上を取るのは「普通に国語が得意」なレベルではまず無理な問題内容(62.5%の75点に達すれば上出来)である、英語は90点台からは上に伸ばすのが急に難しくなる、といった性格がある。
つまり、センター試験と同じように、東大の2次試験にも「意外に楽に伸ばせる得点範囲」とか、「ここから先は、急にコスト・パフォーマンスが落ちる」といった独特の”特性”が備わっているのだ。
それを無理してやみくもに目標得点を上げすぎると、目標を絞り込んだ勉強ができない。要するに、「残り1年」ではこなせない非現実的な受験計画になってしまうのである。
それより、「悪くてもこのくらい取れる」というラインをしっかり見据え、その目標に向かって日々の勉強計画を組み立てたほうが、はるかに現実的である。この発想こそ、「やるべきことを」を絞り込み、必要なことだけを反復強化する和田式の要領勉強術である。
2次試験の得点配分ポイント
センター試験と2次試験について、全体的な目標ラインを定めたあとは、2次試験で必要な科目毎に細かい目標点を設定する。そして、トータルの目標得点を科目ごとに配分するわけだが、本書では。「しのぎ」ライン、「クリア」ライン、「勝負」ラインと称する3段階の目標ラインを設定する。
この節以降、ひんぱんに用いられるキーワードなので、しっかり把握してほしい。注意してほしいのは、科目によっても、あるいは文系・理系の別によっても、それぞれの目標ラインの点数が違ってくることである。それぞれ簡単に説明しておこう。
コストパフォーマンスを考えた「現実的な目標設定」が命
科目別の目標得点を設定するときには、「悪くてもこのぐらい」という発想は重要だ。「やれば伸びるだろう」という”希望的観測”だけでむやみに目標ラインを上に設定しないほうがよい。
2次試験では、たとえば文系の国語で96点(80%)以上を取るのは「普通に国語が得意」なレベルではまず無理な問題内容(62.5%の75点に達すれば上出来)である、英語は90点台からは上に伸ばすのが急に難しくなる、といった性格がある。
つまり、センター試験と同じように、東大の2次試験にも「意外に楽に伸ばせる得点範囲」とか、「ここから先は、急にコスト・パフォーマンスが落ちる」といった独特の”特性”が備わっているのだ。
それを無理してやみくもに目標得点を上げすぎると、目標を絞り込んだ勉強ができない。要するに、「残り1年」ではこなせない非現実的な受験計画になってしまうのである。
それより、「悪くてもこのくらい取れる」というラインをしっかり見据え、その目標に向かって日々の勉強計画を組み立てたほうが、はるかに現実的である。この発想こそ、「やるべきことを」を絞り込み、必要なことだけを反復強化する和田式の要領勉強術である。
2次試験の得点配分ポイント
センター試験と2次試験について、全体的な目標ラインを定めたあとは、2次試験で必要な科目毎に細かい目標点を設定する。そして、トータルの目標得点を科目ごとに配分するわけだが、本書では。「しのぎ」ライン、「クリア」ライン、「勝負」ラインと称する3段階の目標ラインを設定する。
この節以降、ひんぱんに用いられるキーワードなので、しっかり把握してほしい。注意してほしいのは、科目によっても、あるいは文系・理系の別によっても、それぞれの目標ラインの点数が違ってくることである。それぞれ簡単に説明しておこう。
PR
- 05/23/23:07
- 平成22年度大学入試
- コメント:0
- トラックバック:
- トラックバックURLはこちら